326周年 [音楽]
1717年12月の初旬、東部ドイツの小さな町ケーテンに一人の宮廷楽長が着任した。32歳、一つ年上の妻と、子供が4人。気鋭の音楽家として、既にその名は音楽好きの王侯貴族の間では知れわたっていた。
彼の前職はヴァイマルの宮廷礼拝堂のオルガニスト兼宮廷楽師であった。それを務めた9年の間に、彼が生涯に残したオルガン曲の大半が作曲されている。『トッカータとフーガ ニ短調』といえば、今では彼の代表作として知られる名曲だ。同時に、今日も歌い継がれる教会用のカンタータを多数作曲した。
彼の雇い主はヴァイマルの領主、ヴィルヘルム・エルンスト公。彼と同じルター派正統主義の熱心な信者だった。宗教改革の創始者マルティン・ルターは無類の音楽好きであったようで、カトリックの教会では信者が聖歌隊の歌を聴くだけであったのに対し、ルターはドイツ語の賛美歌を作って信者が自ら歌うようにした。そういう伝統もあって、領主がルター派の土地では教会音楽が盛んだったのである。

(ヴァイマルのエルンスト城)
ヴァイマルの宮廷音楽家として、彼の人生は順風満帆だったが、この町の宮廷事情はややこしいものだった。過去の様々な経緯から、領主権がヴィルヘルム・エルンスト公とその従弟エルンスト・アウグストとの間で分有され、争い事が絶えなかったのだ。しかもエルンスト・アウグストは大変な音楽好きで、自らは雇い主でないのに、宮廷楽師の彼を自分の館に頻繁に招き、演奏を楽しむ。そのことがヴィルヘルム・エルンスト公の不興を買っていた。
彼がヴァイマルを去ることになった原因は、前年に死去した宮廷楽長の後任を彼が自認していたのに、雇い主が別の人物を任命したことである。自尊心を傷つけられた彼に、ケーテンの領主レオポルド侯爵から声がかかる。領主の宮廷楽長という地位、そして年棒も申し分なかった。彼は辞職を申し出るが、ヴィルヘルム・エルンスト公は首を縦に振らず、仕舞には彼を一ヶ月も牢屋に入れてしまった。
外界との交わりを絶たれ、たった一人で過ごす「不快で退屈で、楽器のない」拘禁生活。それでも彼は自らの主張を曲げず、一説によればこの間に『平均率クラヴィーア曲集第一巻』の構想を練っていたというから、やはり並大抵の男ではない。1717年12月2日。結局ヴィルヘルム・エルンスト公が根負けする形で彼は釈放され、一家を連れてヴァイマルの北方約100kmのケーテンへと旅立った。

(現在のケーテン)
彼が着任した当時、ケーテンは人口3千人ほどの小さな町だったという。領主のレオポルド侯爵は23歳の若さながら優れた音楽愛好家で、自らもヴィオラの名手であった。
「レオポルド侯は、物心のついた頃からお音楽が好きだった。男の子なら誰でも飛びつく『兵士の人形』」より『音楽家』を欲しがり、13歳の時には早くも母にねだって三人の音楽家を雇い入れたというから、生まれつき音楽に対する感性を持ち合わせていたのだろう。」
(引用書 後述)
だが、以前の雇い主とは異なり、レオポルド侯爵はカルヴァン派に属していた。禁欲的なカルヴァン派は「礼拝中に美しい音楽に心を奪われてはならない」という立場であるため、ケーテンでは教会用のオルガン曲も教会カンタータもお呼びではない。その代わりに、教会音楽から離れた室内楽はレオポルド侯爵の大いに望むところだ。この小さな町には不釣合いな18人もの楽士団を率いて、楽長の彼は侯爵の期待に応えていく。「楽興の時」とはまさにこうした日々のことを指すのだろう。ケーテンの城を舞台に、歴史に名を残す数々の室内楽曲が生み出された。三曲の『ヴァイオリン協奏曲』、ブランデンブルク辺境伯クリスチャン・ルートヴィヒに献呈されたことでその名がついた協奏曲集(原題は『種々の楽器による協奏曲』)が、その代表作と言えようか。
こうした作品とは別に、この時期の彼は個々の楽器の持つ可能性を極限まで追求するような器楽曲も多数残している。
「『楽興』の言葉にふさわしい音楽の悦びにあふれた協奏曲とは対照的に、ソロやデュオのための作品には、しばしば余計なものをそぎ落としたストイックな美しさが漂っている。」
(引用書 後述)
『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』、『無伴奏チェロのための組曲』、『無伴奏フルートのためのパルティータ』、『平均率クラヴィーア曲集第一巻』、『インヴェンションとシンフォニア』、『フランス組曲』、『イギリス組曲』・・・と並べてみれば、ケーテンの宮廷での彼の音楽生活がいかに充実した日々であったかが解ろうというものだ。
「ヴィヴァルディに代表される、耳当たりのいいイタリア風の器楽曲が全盛だった時代に、これほど凝縮された表情をたたえた密度の濃い作品を書けたのは、レオポルド侯自身がこのような音楽に魅せられたからに違いないし、またこのような作品を演奏できる能力を備えた楽団のメンバーがいたからだった。作曲家が自分の創造力を優先させる19世紀以降と違い、当時の作曲はあくまで実際の演奏を前提としたものだったから、作曲家は実際に使える奏者の能力を考えながら、曲の構想を練らなければならなかったのである。」
(引用書 後述)
優れた作曲家と演奏家、そしてその良き理解者である領主との巡り合い。こうしたケーテンでの日々があったからこそ、後に「音楽の父」として歴史上比類なき存在となる彼があり得たのだとも言える。その巡り合わせは、人類史上の一つの奇跡だったといっていいのかもしれない。
ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)。2011年の今日3月21日は、彼の生誕から326周年にあたる。

悲しみや、やり場のない怒りに取り付かれてしまった時、私は彼の『オブリガード・チェンバロとヴァイオリンのための六つのソナタ』 BWV1014~1019 を聴くことが多い。この作品集はヴァイオリンとチェンバロのデュオなのだが、チェンバロの左手が通奏低音の伴奏部分であるの対して右手は一つの独奏楽器のようなパートを受け持つので、ヴァイオリンと合わせると事実上のトリオのような演奏になる。

夜の月に照らされた岩と雪の山々を見つめているような、そんな曲想は、ささくれてしまった自分の心に理性を取り戻そうとする時に、いつの間にか私をクールダウンしてくれる。今度の震災の後も、やはりこの曲を聴いてみたくなった。
「なかでも痛切な空気に貫かれた<第五番>は出色だ。『ヘ短調』という哀切な調性で書かれたこの作品は、中間の楽章<たいていは第三楽章>に調性の異なる楽章をはさむという一般的な習慣にさからい、すべて短調で作曲された。とくに一貫して重音を奏でつづけるヴァイオリンと、分散和音を奏でつづけるチェンバロが拮抗する第三楽章は、あの月から降っていた銀の光のヴェールのように、冷たく透き通った美しさに満ちている。」
(『バッハへの旅』 加藤浩子 著、東京書籍)
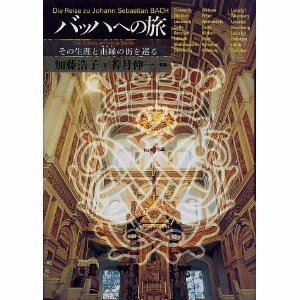
作曲されたのは1720年頃だという。その年の夏、バッハはレオポルド侯のお供で保養地のカールスバード(現在のチェコ共和国のカルロヴィ・ヴァリ)に出かけ、ケーテンに戻ってみると、12年連れ添った妻(マリア・バルバラ)が亡くなっていて既に埋葬された後だったことを知らされる。『オブリガード・チェンバロとヴァイオリンのための六つのソナタ』 第五番が湛える哀調は、その悲しみの中で作られたものなのだろうか。
だがその翌年にバッハは12歳年下の宮廷歌手アンナ・マグダレーナを娶り、その後彼女との間に多くの子を成して、音楽家としての道を邁進した。現在のドイツから外に出ることは終生なかったが、彼が音楽史上に残したものは世界共通の、とてつもなく大きな遺産であったと言うほかはない。
彼の前職はヴァイマルの宮廷礼拝堂のオルガニスト兼宮廷楽師であった。それを務めた9年の間に、彼が生涯に残したオルガン曲の大半が作曲されている。『トッカータとフーガ ニ短調』といえば、今では彼の代表作として知られる名曲だ。同時に、今日も歌い継がれる教会用のカンタータを多数作曲した。
彼の雇い主はヴァイマルの領主、ヴィルヘルム・エルンスト公。彼と同じルター派正統主義の熱心な信者だった。宗教改革の創始者マルティン・ルターは無類の音楽好きであったようで、カトリックの教会では信者が聖歌隊の歌を聴くだけであったのに対し、ルターはドイツ語の賛美歌を作って信者が自ら歌うようにした。そういう伝統もあって、領主がルター派の土地では教会音楽が盛んだったのである。

(ヴァイマルのエルンスト城)
ヴァイマルの宮廷音楽家として、彼の人生は順風満帆だったが、この町の宮廷事情はややこしいものだった。過去の様々な経緯から、領主権がヴィルヘルム・エルンスト公とその従弟エルンスト・アウグストとの間で分有され、争い事が絶えなかったのだ。しかもエルンスト・アウグストは大変な音楽好きで、自らは雇い主でないのに、宮廷楽師の彼を自分の館に頻繁に招き、演奏を楽しむ。そのことがヴィルヘルム・エルンスト公の不興を買っていた。
彼がヴァイマルを去ることになった原因は、前年に死去した宮廷楽長の後任を彼が自認していたのに、雇い主が別の人物を任命したことである。自尊心を傷つけられた彼に、ケーテンの領主レオポルド侯爵から声がかかる。領主の宮廷楽長という地位、そして年棒も申し分なかった。彼は辞職を申し出るが、ヴィルヘルム・エルンスト公は首を縦に振らず、仕舞には彼を一ヶ月も牢屋に入れてしまった。
外界との交わりを絶たれ、たった一人で過ごす「不快で退屈で、楽器のない」拘禁生活。それでも彼は自らの主張を曲げず、一説によればこの間に『平均率クラヴィーア曲集第一巻』の構想を練っていたというから、やはり並大抵の男ではない。1717年12月2日。結局ヴィルヘルム・エルンスト公が根負けする形で彼は釈放され、一家を連れてヴァイマルの北方約100kmのケーテンへと旅立った。

(現在のケーテン)
彼が着任した当時、ケーテンは人口3千人ほどの小さな町だったという。領主のレオポルド侯爵は23歳の若さながら優れた音楽愛好家で、自らもヴィオラの名手であった。
「レオポルド侯は、物心のついた頃からお音楽が好きだった。男の子なら誰でも飛びつく『兵士の人形』」より『音楽家』を欲しがり、13歳の時には早くも母にねだって三人の音楽家を雇い入れたというから、生まれつき音楽に対する感性を持ち合わせていたのだろう。」
(引用書 後述)
だが、以前の雇い主とは異なり、レオポルド侯爵はカルヴァン派に属していた。禁欲的なカルヴァン派は「礼拝中に美しい音楽に心を奪われてはならない」という立場であるため、ケーテンでは教会用のオルガン曲も教会カンタータもお呼びではない。その代わりに、教会音楽から離れた室内楽はレオポルド侯爵の大いに望むところだ。この小さな町には不釣合いな18人もの楽士団を率いて、楽長の彼は侯爵の期待に応えていく。「楽興の時」とはまさにこうした日々のことを指すのだろう。ケーテンの城を舞台に、歴史に名を残す数々の室内楽曲が生み出された。三曲の『ヴァイオリン協奏曲』、ブランデンブルク辺境伯クリスチャン・ルートヴィヒに献呈されたことでその名がついた協奏曲集(原題は『種々の楽器による協奏曲』)が、その代表作と言えようか。
こうした作品とは別に、この時期の彼は個々の楽器の持つ可能性を極限まで追求するような器楽曲も多数残している。
「『楽興』の言葉にふさわしい音楽の悦びにあふれた協奏曲とは対照的に、ソロやデュオのための作品には、しばしば余計なものをそぎ落としたストイックな美しさが漂っている。」
(引用書 後述)
『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』、『無伴奏チェロのための組曲』、『無伴奏フルートのためのパルティータ』、『平均率クラヴィーア曲集第一巻』、『インヴェンションとシンフォニア』、『フランス組曲』、『イギリス組曲』・・・と並べてみれば、ケーテンの宮廷での彼の音楽生活がいかに充実した日々であったかが解ろうというものだ。
「ヴィヴァルディに代表される、耳当たりのいいイタリア風の器楽曲が全盛だった時代に、これほど凝縮された表情をたたえた密度の濃い作品を書けたのは、レオポルド侯自身がこのような音楽に魅せられたからに違いないし、またこのような作品を演奏できる能力を備えた楽団のメンバーがいたからだった。作曲家が自分の創造力を優先させる19世紀以降と違い、当時の作曲はあくまで実際の演奏を前提としたものだったから、作曲家は実際に使える奏者の能力を考えながら、曲の構想を練らなければならなかったのである。」
(引用書 後述)
優れた作曲家と演奏家、そしてその良き理解者である領主との巡り合い。こうしたケーテンでの日々があったからこそ、後に「音楽の父」として歴史上比類なき存在となる彼があり得たのだとも言える。その巡り合わせは、人類史上の一つの奇跡だったといっていいのかもしれない。
ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)。2011年の今日3月21日は、彼の生誕から326周年にあたる。

悲しみや、やり場のない怒りに取り付かれてしまった時、私は彼の『オブリガード・チェンバロとヴァイオリンのための六つのソナタ』 BWV1014~1019 を聴くことが多い。この作品集はヴァイオリンとチェンバロのデュオなのだが、チェンバロの左手が通奏低音の伴奏部分であるの対して右手は一つの独奏楽器のようなパートを受け持つので、ヴァイオリンと合わせると事実上のトリオのような演奏になる。

夜の月に照らされた岩と雪の山々を見つめているような、そんな曲想は、ささくれてしまった自分の心に理性を取り戻そうとする時に、いつの間にか私をクールダウンしてくれる。今度の震災の後も、やはりこの曲を聴いてみたくなった。
「なかでも痛切な空気に貫かれた<第五番>は出色だ。『ヘ短調』という哀切な調性で書かれたこの作品は、中間の楽章<たいていは第三楽章>に調性の異なる楽章をはさむという一般的な習慣にさからい、すべて短調で作曲された。とくに一貫して重音を奏でつづけるヴァイオリンと、分散和音を奏でつづけるチェンバロが拮抗する第三楽章は、あの月から降っていた銀の光のヴェールのように、冷たく透き通った美しさに満ちている。」
(『バッハへの旅』 加藤浩子 著、東京書籍)
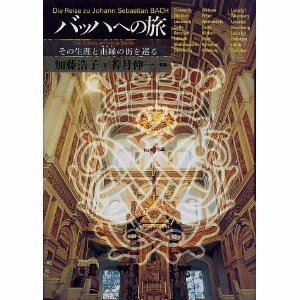
作曲されたのは1720年頃だという。その年の夏、バッハはレオポルド侯のお供で保養地のカールスバード(現在のチェコ共和国のカルロヴィ・ヴァリ)に出かけ、ケーテンに戻ってみると、12年連れ添った妻(マリア・バルバラ)が亡くなっていて既に埋葬された後だったことを知らされる。『オブリガード・チェンバロとヴァイオリンのための六つのソナタ』 第五番が湛える哀調は、その悲しみの中で作られたものなのだろうか。
だがその翌年にバッハは12歳年下の宮廷歌手アンナ・マグダレーナを娶り、その後彼女との間に多くの子を成して、音楽家としての道を邁進した。現在のドイツから外に出ることは終生なかったが、彼が音楽史上に残したものは世界共通の、とてつもなく大きな遺産であったと言うほかはない。
2011-03-21 23:45
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0