師走の初日 [季節]
「十一月二十七日―― 昨夜の風雨は今朝なごりなく晴れ、日うららかに昇りぬ。屋後の丘に立ちて望めば富士山真白に連山の上に聳ゆ。風清く気澄めり。
げに初冬の朝なるかな。
田面(たおも)に水あふれ、林影倒(さかしま)に写れり。」
「十二月二日―― 今朝霜、雪の如く朝日にきらめきて美事なり。暫くして薄雲かかり日光寒し。」
(『武蔵野』 国木田独歩 著、新潮文庫)
明治29年の秋から翌年の春の初めまで、現在の東京・渋谷の松濤町に住んでいた国木田独歩の日記に残された、今頃の東京はこんな風だった。その当時、独歩の住まいのあたりはまだ「渋谷村」で、現在の環状六号(山手通り)の内側でさえ、武蔵野の風景が残っていた頃のことである。丘に立つと連山の上に富士の高嶺が聳えていたというから、丹沢や道志の山々がよく見えていたのだろう。
今は七十二候でいうと「小雪」の末候にあたる「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」。柑橘類の実が黄ばむ頃という意味で、まさにこれからがミカン類の季節である。今年は例年よりも寒さの訪れが早くなり、私も師走の到来を待たずに通勤用のコートを着ることになったが、ともかくも年の暮れまで残すところあと一ヶ月である。
11月は公私共に何かと忙しく、好きな山歩きも文化の日に三ツ峠山に登っただけになってしまった。やはり一ヶ月も間が空いてしまうと、土の道や落葉を踏む感触が恋しくなる。そんな訳で、この土曜日の午後に少しだけ時間を見つけて、自宅の近くの小石川植物園を久しぶりに訪れた。
.jpg)
(小石川植物園)
正門を入り、いつものように正面の坂道を登る。今は特に花の時期でもないことに加え、今日は昼過ぎまで小雨混じりの天候だったから、訪れる人も僅かである。
春は恰好のお花見スポットになるサクラの林も木々は殆ど葉を落とし、園内は晩秋を通り越して初冬の風情だ。どこかヨーロッパの公園を思わせる光景だが、ベンチに座って時を過ごす人もいない。

落葉がちり積もったサクラ林とは対照的に、木々の紅葉が一際鮮やかな一角が、その北側ある。イロハモミジの並木である。ここは園内でも人気の撮影スポットであるらしく、大きなカメラを構えた愛好家が何人か陣取っていた。

冬至まであと三週間。午後3時に近くなると、師走の太陽はもう傾いている。そして北風が冷たい。「薄雲かかり日光寒し」という国木田独歩の言葉が身にしみる。

イロハモミジの紅葉のトンネルを越えると、見上げれば首が痛くなるほど背の高い一本のイチョウの木が立っている。「精子発見のイチョウ」として知られる、この植物園のシンボルの一つだ。

イチョウの胚珠の中で精子が泳ぐ、そのことを明治29年に世界で始めて発見したのは、当時の帝国大学理科大学(現・東京大学理学部)の平瀬作五郎(当時40歳)という助手であった。平瀬は福井藩中学校を出て油絵を志し、帝国大学理科大学には画工として採用された。つまり、平瀬は学者ではなかったのだが、勤務を続ける間に植物学に興味を持ち、イチョウの研究を始めたそうである。それが世界初の「裸子植物における精子の発見」につながり、この年の10月に論文として発表されたという。(冒頭に引用した国木田独歩が渋谷村に住み始めたのとちょうど同じ頃である。)
この業績によって平瀬には、同じくソテツの精子を発見した理学博士の池野成一郎と共に、大正2年に日本学士院の恩賜賞が授与された。平瀬のような「現場力」は、やはり日本のものなのである。
この大イチョウを過ぎると、植物園の中は落葉樹の雑木林になる。先ほどの大イチョウと同じぐらい背の高いスズカケノキやユリノキが続く。スズカケノキはいわゆるプラタナスの一種だが、街路樹としてよく見かけるタイプのプラタナスよりもずっと背の高いものだ。文字通り鈴のような丸い実を落とすので、我家の子供達が小さかった頃は、冬の散歩というと、ここでその丸い実を割って遊んだりしたものだった。大きな落葉をザクザクと踏みながら歩くこの一角は、園内でも私の好きなスポットである。

(大きなユリノキ)
やがて雑木林が終わり、カリンの林と針葉樹林を過ぎると、道は下り坂になって日本庭園に出る。池のほとりを歩いていると、日当たりの良い所では紅葉が見事だ。陽はまた一段と傾いてきたが、青い空がだいぶ広がるようになった。



正門から園内を左回りに一周するように歩いて来たが、終わりは近い。多様な紅葉を眺め、落ち葉を踏みながら更に歩き続けると、メタセコイアの林に出た。背が高く、すっきりとしたその姿が印象的なメタセコイアは、この季節になるとカラマツのような黄葉を見せる。傾いていく陽に照らされて、今日はその黄葉が夕焼け色である。

「真直(まっすぐ)な路で両側とも十分に黄葉した林が四五丁も続く処に出ることがある。この路を独り静かに歩むことのどんなに楽しかろう。右側の林の頂は夕照鮮かにかがやいている。おりおり落葉の音が聞こえるばかり、あたりはいかにもしんとして淋しい。前にも後ろにも人影見えず、誰にも遇わず。もしそれが木葉落ちつくしたころならば、路は落葉に埋もれて、一足ごとにがさがさと音がする、林は奥まで見すかされ、梢の先は針のごとく細く蒼空を指している。なおさら人に遇わない。いよいよ淋しい。」
(前掲書)
東京の都心で国木田独歩のように散歩をしながら、今年最後の紅葉に触れた一時。たとえ植物園の中であっても、やはり自然に触れるのは気分がいいものだ。
寒さの季節は既に始まっているが、これからもうまく時間を見つけて、寒さの中の自然を楽しむようにして行こう。
げに初冬の朝なるかな。
田面(たおも)に水あふれ、林影倒(さかしま)に写れり。」
「十二月二日―― 今朝霜、雪の如く朝日にきらめきて美事なり。暫くして薄雲かかり日光寒し。」
(『武蔵野』 国木田独歩 著、新潮文庫)
明治29年の秋から翌年の春の初めまで、現在の東京・渋谷の松濤町に住んでいた国木田独歩の日記に残された、今頃の東京はこんな風だった。その当時、独歩の住まいのあたりはまだ「渋谷村」で、現在の環状六号(山手通り)の内側でさえ、武蔵野の風景が残っていた頃のことである。丘に立つと連山の上に富士の高嶺が聳えていたというから、丹沢や道志の山々がよく見えていたのだろう。
今は七十二候でいうと「小雪」の末候にあたる「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」。柑橘類の実が黄ばむ頃という意味で、まさにこれからがミカン類の季節である。今年は例年よりも寒さの訪れが早くなり、私も師走の到来を待たずに通勤用のコートを着ることになったが、ともかくも年の暮れまで残すところあと一ヶ月である。
11月は公私共に何かと忙しく、好きな山歩きも文化の日に三ツ峠山に登っただけになってしまった。やはり一ヶ月も間が空いてしまうと、土の道や落葉を踏む感触が恋しくなる。そんな訳で、この土曜日の午後に少しだけ時間を見つけて、自宅の近くの小石川植物園を久しぶりに訪れた。
.jpg)
(小石川植物園)
正門を入り、いつものように正面の坂道を登る。今は特に花の時期でもないことに加え、今日は昼過ぎまで小雨混じりの天候だったから、訪れる人も僅かである。
春は恰好のお花見スポットになるサクラの林も木々は殆ど葉を落とし、園内は晩秋を通り越して初冬の風情だ。どこかヨーロッパの公園を思わせる光景だが、ベンチに座って時を過ごす人もいない。

落葉がちり積もったサクラ林とは対照的に、木々の紅葉が一際鮮やかな一角が、その北側ある。イロハモミジの並木である。ここは園内でも人気の撮影スポットであるらしく、大きなカメラを構えた愛好家が何人か陣取っていた。

冬至まであと三週間。午後3時に近くなると、師走の太陽はもう傾いている。そして北風が冷たい。「薄雲かかり日光寒し」という国木田独歩の言葉が身にしみる。

イロハモミジの紅葉のトンネルを越えると、見上げれば首が痛くなるほど背の高い一本のイチョウの木が立っている。「精子発見のイチョウ」として知られる、この植物園のシンボルの一つだ。

イチョウの胚珠の中で精子が泳ぐ、そのことを明治29年に世界で始めて発見したのは、当時の帝国大学理科大学(現・東京大学理学部)の平瀬作五郎(当時40歳)という助手であった。平瀬は福井藩中学校を出て油絵を志し、帝国大学理科大学には画工として採用された。つまり、平瀬は学者ではなかったのだが、勤務を続ける間に植物学に興味を持ち、イチョウの研究を始めたそうである。それが世界初の「裸子植物における精子の発見」につながり、この年の10月に論文として発表されたという。(冒頭に引用した国木田独歩が渋谷村に住み始めたのとちょうど同じ頃である。)
この業績によって平瀬には、同じくソテツの精子を発見した理学博士の池野成一郎と共に、大正2年に日本学士院の恩賜賞が授与された。平瀬のような「現場力」は、やはり日本のものなのである。
この大イチョウを過ぎると、植物園の中は落葉樹の雑木林になる。先ほどの大イチョウと同じぐらい背の高いスズカケノキやユリノキが続く。スズカケノキはいわゆるプラタナスの一種だが、街路樹としてよく見かけるタイプのプラタナスよりもずっと背の高いものだ。文字通り鈴のような丸い実を落とすので、我家の子供達が小さかった頃は、冬の散歩というと、ここでその丸い実を割って遊んだりしたものだった。大きな落葉をザクザクと踏みながら歩くこの一角は、園内でも私の好きなスポットである。

(大きなユリノキ)
やがて雑木林が終わり、カリンの林と針葉樹林を過ぎると、道は下り坂になって日本庭園に出る。池のほとりを歩いていると、日当たりの良い所では紅葉が見事だ。陽はまた一段と傾いてきたが、青い空がだいぶ広がるようになった。



正門から園内を左回りに一周するように歩いて来たが、終わりは近い。多様な紅葉を眺め、落ち葉を踏みながら更に歩き続けると、メタセコイアの林に出た。背が高く、すっきりとしたその姿が印象的なメタセコイアは、この季節になるとカラマツのような黄葉を見せる。傾いていく陽に照らされて、今日はその黄葉が夕焼け色である。

「真直(まっすぐ)な路で両側とも十分に黄葉した林が四五丁も続く処に出ることがある。この路を独り静かに歩むことのどんなに楽しかろう。右側の林の頂は夕照鮮かにかがやいている。おりおり落葉の音が聞こえるばかり、あたりはいかにもしんとして淋しい。前にも後ろにも人影見えず、誰にも遇わず。もしそれが木葉落ちつくしたころならば、路は落葉に埋もれて、一足ごとにがさがさと音がする、林は奥まで見すかされ、梢の先は針のごとく細く蒼空を指している。なおさら人に遇わない。いよいよ淋しい。」
(前掲書)
東京の都心で国木田独歩のように散歩をしながら、今年最後の紅葉に触れた一時。たとえ植物園の中であっても、やはり自然に触れるのは気分がいいものだ。
寒さの季節は既に始まっているが、これからもうまく時間を見つけて、寒さの中の自然を楽しむようにして行こう。
蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) [季節]
今週から、東京もだいぶこの季節らしくなってきた。家の窓を開け放っていると、朝晩は少し肌寒さを感じるほどだ。9月に暑さがいつまでも続いたせいか、先週末に訪れた近郊の山では紅葉が例年より遅れていたし、東京の街中では金木犀もまだ香らないが、ともかくも秋である。そういえば、今週の月曜日の10月8日は、暦の上では「寒露」だった。

一年を二十四の季節に分けた二十四節気。そのベースになる暦は、言うまでもなく太陰太陽暦である。
朔望月(月の満ち欠けの一周期)は平均すると約29.5日だから、一年を12ヶ月とすると、純粋な太陰暦では一年が354日になる。つまり、太陽暦からは毎年11日ずつ乖離していくので、閏月を19年に7回(=約3年に1回)設けることによってそのずれをなくしたのが太陰太陽暦だ。その際に、太陽の一年間の動きをもとに一年を24の節に分け、太陰暦を補正するための目安とされたのが二十四節気である。
その24の節は12の「中気」と12の「節気」が交互に置かれ、それぞれに季節の名前が付けられている。そして、新月の日から始まる太陰暦の一ヶ月は、その月が含む中気によって決められる。節気から次の節気までが「節月」で、それはあくまでも太陽暦における一ヶ月だ。そして各々の節月の中間点には必ず中気がやって来る。

年の初めを例に取れば、「雨水」を含む月が正月になる。その雨水は一年を通した太陽の位置によって割り出されているから、その約15日前、つまり直前の節気は必ず「立春」なのだが、それでは正月一日、つまり元日が必ず立春なのかというと、そうとは限らない。日付を決めるのはあくまでも月齢だから、雨水の直前の朔日(新月の日)が元日とされ、それは立春の前だったり後だったりする訳だ。いずれにしても、太陰暦が太陽暦からどんどん乖離していくと農耕などには不便だから、それを補正するために用いられた古代中国の知恵である。
この太陰太陽暦、日本では9世紀の後半に渤海使によって伝えられた唐代の「宣明暦」が以後も長く使われたという。それが江戸時代初期の1684年、幕府碁方の安井算哲(後の渋川春海)によって編み出された「貞享暦」へと、実に800年ぶりに改暦されたそうだ。以後、宝暦暦、寛政暦、天保暦へと改暦が続き、明治5年の暮まで太陽太陰暦は続いた。だから、日本人の伝統的な季節感には、当たり前の話だが旧暦の方がフィットしている。(今のように、お正月になって「新春」という言葉使いをしているのに、その後に「大寒」がやって来たり、三月の「桃の節句」に桃の花はまだ咲いていなかったりというのは、やはり変だ。)
その二十四節気は、それぞれが更に初候・次候・末候の3つに分かれるという。「七十二候(しちじゅうにこう)」と呼ばれるもので、これもまた古代中国で考案されたものだ。365÷24÷3だから、要するに約5日ごとに新たな季節がやって来る訳で、これを考え出したのはよほど自然観察の好きな人だったのだろうなどと思ってしまうが、東アジアの中緯度地帯は、それぐらい季節の変化が多彩なのだろう。
七十二候は短い漢文だ。例えば、年の初めの立春では、その初候が「東風解凍(東風が厚い氷を解かし始める)」、次候が「蟄虫始振(冬籠りの虫が動き始める)」、そして末候が「魚上氷(割れた氷の間から魚が飛び出る)」といったような具合である。だが、ここまで視覚的・具体的な表現になると、中国オリジナルのままでは日本の風土に馴染まない部分があったので、古代中国のものがそのまま使われた二十四節気とは異なり、七十二候は何度か日本風に改められたという。先ほど登場した渋川春海なども、それに腕を振るった一人であるようだ。
『日本の七十二候を楽しむ - 旧暦のある暮らし -』(文:白井明大、絵:有賀一広、東邦出版)は、そうした日本版の七十二候を親しみやすく解説した好著である。それぞれの候に込められた季節感の解説に始まって、候のことば、旬の野菜、旬の野鳥、旬の魚介、旬の兆し、そして旬の行事などが見開き二ページで紹介されており、あらためて「なるほど!」と思うことばかりだ。そして、各ページを彩る水彩色の繊細なイラストがやさしい。森と石清水、山の幸と海の幸に恵まれたこの国に生まれ育った幸せをかみしめたくなる一冊である。

今週の月曜日が寒露だったから、その候を本書で調べてみよう。初候は「鴻雁来(がんきたる)」、雁が北から渡ってくる頃という意味で、新暦ではおよそ10月8日~12日頃であるという。今の東京ではさすがにそれを観察は出来ないが、北国ではもうそんな季節なのだろうか。
今日は13日だから、七十二候では寒露の次候である「菊花開(きっかひらく)」の始まりになる。10月の13日~17日頃とある。旬のことばは、旧暦9月9日の「重陽の日」に摘んだ菊の花びらを乾かして詰め物にした「菊枕」。旬の魚介は秋田のはたはた。旬の果物は栗。そして、菊の花が咲く頃に青空が晴れ渡ることを「菊晴れ」と呼ぶと書いてある。今日は朝から空気の爽やかな秋の快晴だが、さしずめこんな日のことを指すのだろうか。
そして、これに続く寒露の末候(10月18日~22日頃)は「蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)」だ。
「秋が深まり、野をにぎわせていたはずのきりぎりすやこおろぎが、明かりや暖かさに惹かれてなのか、人の住まいにこっそり近づくさまを想像すると、ほほえましく思えます。」
(前掲書)
そういえば来週以降は、ずいぶん長い間ご無沙汰してしまった人々と久しぶりに飲む約束を、私は幾つかしている。再会を喜び合いながら、私達はどんな酒を酌み交わすことになるのだろうか。この時期に夜の明かりに誘われるのは、きりぎりすだけではないようである。
そして寒露の末候が終わると、10月23日には「霜降」を迎える。
酒はそろそろ、熱燗をゆっくりやるのがよさそうだ。
夏空の果てに [季節]
9月も10日を過ぎたというのに、今年は厳しい残暑が続いている。
その残暑疲れか、或いは先週の出張疲れか、この週末に私は柄にもなく体調を少し崩してしまって、土日はおとなしくしていることが多かった。本当は体を動かしてシャキッとさせたいところだったが、胃腸の調子が悪くてはそうもいかない。横になって新聞やら本やらを読みながら、ふと窓の外に目をやると、そこにはまだまだ元気な夏空があった。
気象庁のHPから、気象統計を眺めてみると、あらためて気づかされることがある。
日本各地の月別平均気温が平年(昨年までの過去30年間)と比べてどうだったか、それを今年の1月から追ってみたのが以下のグラフの通りだ。各地方ともおしなべて年の初めの冬は平年よりかなり寒く、それが夏になると一転して平年よりかなり暑くなったことが一目瞭然である。特に、東北・関東甲信・北陸などは本当に暑い夏になった。(小さな数字のように見えるが、一ヶ月の平均気温が平年より2度高いというのは、実は相当なことである。)

東京などについて言えば、今年の夏は暑いばかりでなく、来る日も来る日も太陽が照っていたという印象がある。逆に言えば、雨が降った日が非常に少なかった。8月の各地の日照時間と降水量について、それぞれ平年の何%水準であったかを見てみたのが次のグラフだ。大まかに言えば、日照時間と降水量はトレード・オフの関係になる、そんな様子がよく表れている。

ここではっきり言えるのは、とりわけ東北地方と関東甲信地方において、今年の8月は平年よりも日照時間がかなり長く、反対に降水量が非常に少なかったということだ。首都圏を抱える関東甲信では、雨の量は平年の半分だった。
そういう事実を踏まえながら、あらためて先週のニュースをフォローしてみると、9月7日(金)に国土交通省関東地方整備局が、「利根川上流ダム群の貯水量が大幅に減少」というメッセージを発していた。利根川上流の8つのダム(有効貯水容量の合計は3億4,350万㎥)の貯水率は、7月1日現在では100%だったのが、7月末からの少雨のために水嵩が減り続けて、9月7日の時点で貯水率40%となり、これは平年の54%の水準でしかないそうだ。特に、8つの中で最大規模を誇る矢木沢ダム(群馬県、有効貯水容量1億1,550万㎥)の貯水率が僅か6%しかないことの影響が大きいという。
矢木沢ダムは群馬・新潟両県の県境近く、奥利根湖と呼ばれる人工湖を形作るダムである。温泉地で有名な水上から利根川を更にさかのぼり、谷川岳の険しい谷を形成する湯檜曽川を左に分けて、右の谷を更にずっと奥深く登ったところにある、まさに利根川の最源流だ。
この矢木沢ダムに一番近い藤原という地点のアメダスのデータによると、今年8月の日照時間は208時間で平年の142%だったのに対して、降水量は51ミリで平年の29%だった。まさに日照りによる水不足である。関東地方整備局によると、こうした状況がこのまま続けば、9月11日から利根川水系で10%の取水制限を行うことになるという。

私が小学校二年生の夏に、父の転勤で大阪から東京にやって来た昭和39年。その夏の東京は深刻な水不足から「東京砂漠」と呼ばれ、小学生は水筒を持って学校に通ったものだった。オリンピックの開催を間近にして水の消費量が急速に増えていた当時の東京は、多摩川水系の小河内ダム(奥多摩湖)が唯一の頼みの綱で、それがピンチになったためだった。
以来、水供給インフラの整備が進められて、首都圏への現在の水供給は、多摩川水系の他に相模川水系、荒川水系、そして利根川水系からの水が利用されている。それらの河川に設けられたダムの有効貯水容量の合計は9億1千万㎥を越え、そのキャパに対して9月7日時点での貯水率は67%で、それは平年の82%水準であるという。そうした合計の数字で見れば、首都圏が今すぐに深刻な水不足に陥るというものでもないのだろうが、利根川水系に限って言えば、10%の取水制限はそれなりの影響を流域には与えそうである。
首都圏最大の水がめである小河内ダムと、それに次ぐ宮ヶ瀬ダム(相模川水系)は山の上から眺めたことがあるが、同じ1億㎥クラスのキャパを持つ矢木沢ダムは、私はまだこの目で見たことがない。それを今、どこかの山の上から眺めたならば、貯水率6%のその姿にどんな思いがすることだろう。
私たちはいつの間にか、どこへ行ってもペットボトルの水を買える時代を迎え、上下水道のインフラもよく整備されているので、普段の生活の中で水に困るというような事態を想像することが難しい。そして、便利な世の中にうつつをぬかし、自分一人がいつも通りの暮らしを続けていくために世の中でどれくらいの水が使われていることになるのかを考えることもない。仮に考えたところで、そんなことは見当もつかないだろう。
だが、私たちが山歩きをするたびに、生きるためには水がどれほど大切なものであるかを考えさせられるし、その一方でわが国は何とも水資源に恵まれた国であることを思わざるを得ない。山の中で何の問題もなく湧水をそのまま飲める国や、国土の2/3に森林が残る国などというのは、世界の中でも限られているのだから。
明日は二百二十日。本来なら台風上陸のシーズンだが、現時点での週間天気予報にその兆候はない。本当に困った事態になる前に、水供給のありがたさを改めて考えてみた方がいいのかもしれない。
その残暑疲れか、或いは先週の出張疲れか、この週末に私は柄にもなく体調を少し崩してしまって、土日はおとなしくしていることが多かった。本当は体を動かしてシャキッとさせたいところだったが、胃腸の調子が悪くてはそうもいかない。横になって新聞やら本やらを読みながら、ふと窓の外に目をやると、そこにはまだまだ元気な夏空があった。
気象庁のHPから、気象統計を眺めてみると、あらためて気づかされることがある。
日本各地の月別平均気温が平年(昨年までの過去30年間)と比べてどうだったか、それを今年の1月から追ってみたのが以下のグラフの通りだ。各地方ともおしなべて年の初めの冬は平年よりかなり寒く、それが夏になると一転して平年よりかなり暑くなったことが一目瞭然である。特に、東北・関東甲信・北陸などは本当に暑い夏になった。(小さな数字のように見えるが、一ヶ月の平均気温が平年より2度高いというのは、実は相当なことである。)

東京などについて言えば、今年の夏は暑いばかりでなく、来る日も来る日も太陽が照っていたという印象がある。逆に言えば、雨が降った日が非常に少なかった。8月の各地の日照時間と降水量について、それぞれ平年の何%水準であったかを見てみたのが次のグラフだ。大まかに言えば、日照時間と降水量はトレード・オフの関係になる、そんな様子がよく表れている。

ここではっきり言えるのは、とりわけ東北地方と関東甲信地方において、今年の8月は平年よりも日照時間がかなり長く、反対に降水量が非常に少なかったということだ。首都圏を抱える関東甲信では、雨の量は平年の半分だった。
そういう事実を踏まえながら、あらためて先週のニュースをフォローしてみると、9月7日(金)に国土交通省関東地方整備局が、「利根川上流ダム群の貯水量が大幅に減少」というメッセージを発していた。利根川上流の8つのダム(有効貯水容量の合計は3億4,350万㎥)の貯水率は、7月1日現在では100%だったのが、7月末からの少雨のために水嵩が減り続けて、9月7日の時点で貯水率40%となり、これは平年の54%の水準でしかないそうだ。特に、8つの中で最大規模を誇る矢木沢ダム(群馬県、有効貯水容量1億1,550万㎥)の貯水率が僅か6%しかないことの影響が大きいという。
矢木沢ダムは群馬・新潟両県の県境近く、奥利根湖と呼ばれる人工湖を形作るダムである。温泉地で有名な水上から利根川を更にさかのぼり、谷川岳の険しい谷を形成する湯檜曽川を左に分けて、右の谷を更にずっと奥深く登ったところにある、まさに利根川の最源流だ。
この矢木沢ダムに一番近い藤原という地点のアメダスのデータによると、今年8月の日照時間は208時間で平年の142%だったのに対して、降水量は51ミリで平年の29%だった。まさに日照りによる水不足である。関東地方整備局によると、こうした状況がこのまま続けば、9月11日から利根川水系で10%の取水制限を行うことになるという。

私が小学校二年生の夏に、父の転勤で大阪から東京にやって来た昭和39年。その夏の東京は深刻な水不足から「東京砂漠」と呼ばれ、小学生は水筒を持って学校に通ったものだった。オリンピックの開催を間近にして水の消費量が急速に増えていた当時の東京は、多摩川水系の小河内ダム(奥多摩湖)が唯一の頼みの綱で、それがピンチになったためだった。
以来、水供給インフラの整備が進められて、首都圏への現在の水供給は、多摩川水系の他に相模川水系、荒川水系、そして利根川水系からの水が利用されている。それらの河川に設けられたダムの有効貯水容量の合計は9億1千万㎥を越え、そのキャパに対して9月7日時点での貯水率は67%で、それは平年の82%水準であるという。そうした合計の数字で見れば、首都圏が今すぐに深刻な水不足に陥るというものでもないのだろうが、利根川水系に限って言えば、10%の取水制限はそれなりの影響を流域には与えそうである。
首都圏最大の水がめである小河内ダムと、それに次ぐ宮ヶ瀬ダム(相模川水系)は山の上から眺めたことがあるが、同じ1億㎥クラスのキャパを持つ矢木沢ダムは、私はまだこの目で見たことがない。それを今、どこかの山の上から眺めたならば、貯水率6%のその姿にどんな思いがすることだろう。
私たちはいつの間にか、どこへ行ってもペットボトルの水を買える時代を迎え、上下水道のインフラもよく整備されているので、普段の生活の中で水に困るというような事態を想像することが難しい。そして、便利な世の中にうつつをぬかし、自分一人がいつも通りの暮らしを続けていくために世の中でどれくらいの水が使われていることになるのかを考えることもない。仮に考えたところで、そんなことは見当もつかないだろう。
だが、私たちが山歩きをするたびに、生きるためには水がどれほど大切なものであるかを考えさせられるし、その一方でわが国は何とも水資源に恵まれた国であることを思わざるを得ない。山の中で何の問題もなく湧水をそのまま飲める国や、国土の2/3に森林が残る国などというのは、世界の中でも限られているのだから。
明日は二百二十日。本来なら台風上陸のシーズンだが、現時点での週間天気予報にその兆候はない。本当に困った事態になる前に、水供給のありがたさを改めて考えてみた方がいいのかもしれない。
秋は河原で [季節]
仙台の南西、東北自動車道の村田JCTから山形自動車道に入ると、道路はやがて深い谷の中へと入り込んでいく。仙台から眺め続けてきた平地と丘ののどかな風景とは異なり、行く手には標高1,000mを超える山々が連なっている。
谷の下を走る国道286号線はここから先が難所で、地図を見るとヘアピン・カーブの連続だ。そして南北に走る山脈を横切る笹谷峠(標高906m)付近は今でも冬は閉鎖され、自動車の通行ができないという。蝦夷の侵入を防ぐために9世紀頃に築かれたという有耶無耶関(うやむやのせき)がこの峠のすぐ南にあったそうだから、古来このあたりは東西を結ぶ山越えの道の要所であったのだろう。
現在の山形自動車道は、その笹谷峠の核心部分を全長3キロ余りのトンネルで楽々と通り過ぎてしまう。そのトンネルを抜けると山形県なのだが、窓の外の山並みは一転して穏やかになり、行く手には明るい平地が眼下に見えてきた。
9月2日の日曜日、私は仙台から半日のバス・ツアーに参加している。
先週の週中から一週間ほど仕事で仙台に滞在することになったのだが、日曜日だけは作業の予定もなく空いていた。かつての職場の先輩で、今は仙台で鉄道会社の経営幹部を務めておられるSさんに連絡を入れてみると、
「ちょうどこの日に職場で企画したバス旅行が予定されているから、よかったらジョインしない?」
とのこと。私は恐縮しつつもそのバスに文字通り「便乗」させていただくことにしていたのだ。
私を含めて総勢26名。もちろんSさん以外は初対面の人たちだが、そんな気が全然しないぐらい気さくで温かみのある方々ばかりだ。午前11時の定刻にバスが発車して早々に配られた缶ビールや清酒で、車内は早くも大いに盛り上がっている。今日は皆お腹を空けてきた。目的地は山形市内の馬見ヶ崎川の河川敷で行なわれている「日本一の芋煮会フェスティバル」なのである。
山形盆地に下りるとバスはいつしか高速を離れ、12時過ぎには目的地の近くに着いてしまった。川の手前でバスを降り、橋を渡って対岸に出ると、そこはもう大変な人出になっている。


山形市や山形商工会議所などが主催する「日本一の・・・」は、今年で24回目を迎えるという。河川敷に直径6mの大鍋を用意し、3万食の芋煮を作るというこのイベント。鍋の中身は水が6トン、酒が50升に醤油が700リットル。具材はサトイモ3トンに山形牛の肉が1.2トン、コンニャク3500枚にネギが3500本というから途方もない量だ。そして、そういうサイズだからクレーンで鍋の蓋を吊るし、建設重機で中味を取り分ける。もちろん、人の口に入るものだから、鍋や機器の衛生管理も徹底している。

東北各地で行われる芋煮鍋と同じようなサトイモ主体の鍋料理が世界のどこか他にもあるのかどうかは知らないが、県外からも人を集めてこんなに盛大に、こんなに大量の芋煮鍋をこんなに大真面目に作るイベントは他にないだろう。今はグローバルな時代。山形市も商工会議所も、どうせなら「世界一の芋煮会」を名乗ってみてはいかがだろう。
河川敷に着いた私たちは、そこに設置された様々なイベント・コーナーをしばらくの間物色していたが、12時50分になると大鍋の前に集合。仮設テントの「芋煮茶屋」へと案内される。この芋煮会では一般には整理券に従って長い行列に並ばないと芋煮にありつけないのだが、今日のバス・ツアーでは「芋煮茶屋」のテーブル席を予め取っていてくれたので、13時から14時半までの間、その席で好きなだけ芋煮を楽しめる趣向になっている。9月に入ってもまだ暑さの厳しい中、列に並ばなくても済むのはありがたい。
それにしても、9月の第一日曜日という、まだ暑いに決まってる時期に熱い鍋を振舞うというのだから、このイベントも不思議なものである。
この「芋煮茶屋」では、飲み物の持ち込みは自由だ。バスの中から通算して何本目になるのかわからない缶ビールを開けていると、お待ちかねの芋煮が運ばれてきた。山形風と庄内風の二種類である。

(左が庄内風、右が山形風の芋煮)
東北各地では秋の風物詩の一つに数えられる「芋煮会」。米に代わる主食として江戸期に栽培が進んだサトイモを主な具材とするこの鍋は、各地で味も具も異なるのだそうだ。私たちの席に運ばれてきたものも、山形風は「醤油味のスープ+牛肉」、庄内風は「味噌味のスープ+豚肉」である。宮城県も基本はこの「味噌味+豚肉」で、仙台味噌が使われるという。
その他には山形県の最上地方のように「醤油味+鶏肉」というパターンや、三陸地方のように魚介類が肉の代わりになるパターンもあるそうだ。このあたり、東北はやはり奥が深いと言うべきか。(青森県だけは芋煮会の習慣がないのは、かつてサトイモ栽培の北限が青森県に届かなかったからだという。)
「この二種類ではどちらが好きですか?」と聞かれると、私は返事に困ってしまう。甲乙つけがたい良さがどちらにもあるので、敢えて一方に軍配を挙げる必要もないのだろうと思う。どちらも美味しかった。今日ご一緒した方々の間では総じて山形バージョンの評価が高かったようだが、それは「牛肉が食べたかった」のが理由だったのかもしれない。
ともかくも二種類の芋煮を楽しみ、皆で賑やかに過ごしていると、一時間半などはあっという間だ。新たな丼が次々に運ばれてくるので、私はそれぞれを二杯ずつ計四杯も食べてしまい、もう満腹である。その一方で、今日ご一緒しているのはみんな鉄道会社の方々だから、「鉄分」の多い私としては、鉄道の話を色々と聞かせていただくのがこの上なくありがたい。興味深いお話の数々に、思わず時を忘れてしまった。

予定の時刻になると、芋煮会の会場ともお別れである。残暑に汗をかき、そして熱い芋煮鍋を食べて更に汗をかいた。馬見ヶ崎川の橋を渡ると、彼方には月山がどっしりとした姿を見せていた。

私たちが再び乗り込んだバスは、山形盆地を更に南へ向かい、米沢にだいぶ近い高畠という所にあるワイナリーに寄った。ここで簡単な見学をした後、お土産物を選んで、後は一路仙台に戻るだけである。

(高畠ワイナリー)
人類の食文化の地図を作ると、インドとミャンマーの間で縦に境界線を引くことが出来るという。そこから東のアジア地域では、一つの鍋を皆でつつく食文化があることで共通しているそうだ。逆にインドから西では、料理を最初から一人分ずつ皿に取り分ける文化だということになる。(そうしないと常にケンカになるから、というのが本当かどうかは知らない。)
とりわけこの日本では、一つの鍋を皆でつつくのが、その集団の中での一体感を醸成するために大切なことだった。秋になると河原に集まり、その秋に採れたサトイモを使って鍋を食べるという習慣が、それぞれのスタイルながら今も各地で続く東北地方。それは私たち日本人の心のルーツを今に伝える地域であるのかもしれない。
山形の名物を味わいながら楽しく過ごした半日。招いてくださったS先輩と、初対面の私を温かく迎えてくださった皆さんには、心からお礼を申し上げたい。
谷の下を走る国道286号線はここから先が難所で、地図を見るとヘアピン・カーブの連続だ。そして南北に走る山脈を横切る笹谷峠(標高906m)付近は今でも冬は閉鎖され、自動車の通行ができないという。蝦夷の侵入を防ぐために9世紀頃に築かれたという有耶無耶関(うやむやのせき)がこの峠のすぐ南にあったそうだから、古来このあたりは東西を結ぶ山越えの道の要所であったのだろう。
現在の山形自動車道は、その笹谷峠の核心部分を全長3キロ余りのトンネルで楽々と通り過ぎてしまう。そのトンネルを抜けると山形県なのだが、窓の外の山並みは一転して穏やかになり、行く手には明るい平地が眼下に見えてきた。
9月2日の日曜日、私は仙台から半日のバス・ツアーに参加している。
先週の週中から一週間ほど仕事で仙台に滞在することになったのだが、日曜日だけは作業の予定もなく空いていた。かつての職場の先輩で、今は仙台で鉄道会社の経営幹部を務めておられるSさんに連絡を入れてみると、
「ちょうどこの日に職場で企画したバス旅行が予定されているから、よかったらジョインしない?」
とのこと。私は恐縮しつつもそのバスに文字通り「便乗」させていただくことにしていたのだ。
私を含めて総勢26名。もちろんSさん以外は初対面の人たちだが、そんな気が全然しないぐらい気さくで温かみのある方々ばかりだ。午前11時の定刻にバスが発車して早々に配られた缶ビールや清酒で、車内は早くも大いに盛り上がっている。今日は皆お腹を空けてきた。目的地は山形市内の馬見ヶ崎川の河川敷で行なわれている「日本一の芋煮会フェスティバル」なのである。
山形盆地に下りるとバスはいつしか高速を離れ、12時過ぎには目的地の近くに着いてしまった。川の手前でバスを降り、橋を渡って対岸に出ると、そこはもう大変な人出になっている。
山形市や山形商工会議所などが主催する「日本一の・・・」は、今年で24回目を迎えるという。河川敷に直径6mの大鍋を用意し、3万食の芋煮を作るというこのイベント。鍋の中身は水が6トン、酒が50升に醤油が700リットル。具材はサトイモ3トンに山形牛の肉が1.2トン、コンニャク3500枚にネギが3500本というから途方もない量だ。そして、そういうサイズだからクレーンで鍋の蓋を吊るし、建設重機で中味を取り分ける。もちろん、人の口に入るものだから、鍋や機器の衛生管理も徹底している。
東北各地で行われる芋煮鍋と同じようなサトイモ主体の鍋料理が世界のどこか他にもあるのかどうかは知らないが、県外からも人を集めてこんなに盛大に、こんなに大量の芋煮鍋をこんなに大真面目に作るイベントは他にないだろう。今はグローバルな時代。山形市も商工会議所も、どうせなら「世界一の芋煮会」を名乗ってみてはいかがだろう。
河川敷に着いた私たちは、そこに設置された様々なイベント・コーナーをしばらくの間物色していたが、12時50分になると大鍋の前に集合。仮設テントの「芋煮茶屋」へと案内される。この芋煮会では一般には整理券に従って長い行列に並ばないと芋煮にありつけないのだが、今日のバス・ツアーでは「芋煮茶屋」のテーブル席を予め取っていてくれたので、13時から14時半までの間、その席で好きなだけ芋煮を楽しめる趣向になっている。9月に入ってもまだ暑さの厳しい中、列に並ばなくても済むのはありがたい。
それにしても、9月の第一日曜日という、まだ暑いに決まってる時期に熱い鍋を振舞うというのだから、このイベントも不思議なものである。
この「芋煮茶屋」では、飲み物の持ち込みは自由だ。バスの中から通算して何本目になるのかわからない缶ビールを開けていると、お待ちかねの芋煮が運ばれてきた。山形風と庄内風の二種類である。
(左が庄内風、右が山形風の芋煮)
東北各地では秋の風物詩の一つに数えられる「芋煮会」。米に代わる主食として江戸期に栽培が進んだサトイモを主な具材とするこの鍋は、各地で味も具も異なるのだそうだ。私たちの席に運ばれてきたものも、山形風は「醤油味のスープ+牛肉」、庄内風は「味噌味のスープ+豚肉」である。宮城県も基本はこの「味噌味+豚肉」で、仙台味噌が使われるという。
その他には山形県の最上地方のように「醤油味+鶏肉」というパターンや、三陸地方のように魚介類が肉の代わりになるパターンもあるそうだ。このあたり、東北はやはり奥が深いと言うべきか。(青森県だけは芋煮会の習慣がないのは、かつてサトイモ栽培の北限が青森県に届かなかったからだという。)
「この二種類ではどちらが好きですか?」と聞かれると、私は返事に困ってしまう。甲乙つけがたい良さがどちらにもあるので、敢えて一方に軍配を挙げる必要もないのだろうと思う。どちらも美味しかった。今日ご一緒した方々の間では総じて山形バージョンの評価が高かったようだが、それは「牛肉が食べたかった」のが理由だったのかもしれない。
ともかくも二種類の芋煮を楽しみ、皆で賑やかに過ごしていると、一時間半などはあっという間だ。新たな丼が次々に運ばれてくるので、私はそれぞれを二杯ずつ計四杯も食べてしまい、もう満腹である。その一方で、今日ご一緒しているのはみんな鉄道会社の方々だから、「鉄分」の多い私としては、鉄道の話を色々と聞かせていただくのがこの上なくありがたい。興味深いお話の数々に、思わず時を忘れてしまった。

予定の時刻になると、芋煮会の会場ともお別れである。残暑に汗をかき、そして熱い芋煮鍋を食べて更に汗をかいた。馬見ヶ崎川の橋を渡ると、彼方には月山がどっしりとした姿を見せていた。
私たちが再び乗り込んだバスは、山形盆地を更に南へ向かい、米沢にだいぶ近い高畠という所にあるワイナリーに寄った。ここで簡単な見学をした後、お土産物を選んで、後は一路仙台に戻るだけである。
(高畠ワイナリー)
人類の食文化の地図を作ると、インドとミャンマーの間で縦に境界線を引くことが出来るという。そこから東のアジア地域では、一つの鍋を皆でつつく食文化があることで共通しているそうだ。逆にインドから西では、料理を最初から一人分ずつ皿に取り分ける文化だということになる。(そうしないと常にケンカになるから、というのが本当かどうかは知らない。)
とりわけこの日本では、一つの鍋を皆でつつくのが、その集団の中での一体感を醸成するために大切なことだった。秋になると河原に集まり、その秋に採れたサトイモを使って鍋を食べるという習慣が、それぞれのスタイルながら今も各地で続く東北地方。それは私たち日本人の心のルーツを今に伝える地域であるのかもしれない。
山形の名物を味わいながら楽しく過ごした半日。招いてくださったS先輩と、初対面の私を温かく迎えてくださった皆さんには、心からお礼を申し上げたい。
梅雨明け十日 [季節]
「海の日」の三連休が明けて、朝から真夏の太陽が照りつけた7月17日(火)に、関東甲信地方の梅雨明けが発表された。早速日本各地には今年一番の暑さがやってきて、こういう時には必ず話題になる館林では39.2度を記録した。いよいよ夏も本番である。
今年を含めて、21世紀に入ってからの12年間の記録から平均値を割り出してみると、関東甲信地方では梅雨入りが6月7日、梅雨明けが7月19日、従って梅雨の期間は42日間というのが相場であるようだ。それに対して今年は梅雨入りが6月9日、明けが7月17日、期間は38日間だったから、タイミングといい長さといい極めて平均的な梅雨だったと言えるかもしれない。

(関東甲信地方の梅雨入りと梅雨明け)
もっとも、梅雨の期間中には必ず日本のどこかが大雨による被害に遭っている。昨年はそれが新潟・福島両県の県境あたりだった。(おかげでJR只見線には未だに復旧していない箇所がある。)そして今年は、何といっても九州北部の豪雨だろう。久留米に住む友人が先週末に写真付きのメールを送ってくれたのだが、巨大な濁流となった筑後川の画像には実に生々しいものがあった。
話は40年以上前にさかのぼる。
人類が地球以外の星に初めて足跡を残した、米アポロ11号の月面着陸。それは1969(昭和44)年の、日本時間では7月21日の早朝の出来事だったのだが、当時私は中学一年生で、その日は夏の臨海学校で千葉の富浦へ合宿に行っていたから、テレビでリアルタイムにそのニュースを見るような機会はなかった。
調べてみると、この年の関東甲信地方の梅雨明けは7月14日だから、私たちが富浦の海で泳ぎ、宇宙の彼方で人類が初めて月に降り立ったのは、その梅雨明けから一週間ほど経った頃のことになる。一般に、梅雨明け後の十日間ほどは夏型の天候が安定すると言われるが、確かに私の中に残るこの時の臨海学校の思い出は、来る日も来る日も青い空と白い雲、穏やかな内房の海、そしてみんな真っ黒になって東京へ帰って来たこと、といったところだろうか。
太平洋高気圧の勢力が強くなって梅雨前線が北へ押し上げられる、その時に前線が通過する場所では強い雨が降ることが多い。子供の頃は、梅雨の終わりといえば激しい雷雨があったりして(大体それは夜だった)、それが止むと一転して太陽が照りつける夏空がやって来た。梅雨というのは、そんな風にかなり明快に明けたものだった。
アポロ・イレブンの年から8年が経った1977(昭和52)年の夏、私は大学生になっていて、久しぶりにビッグな夏休みを迎えることになった。その年の関東甲信地方の梅雨明けは7月21日。私たちは、その梅雨明けを待っていたかのように、ザックを担いで穂高の岳沢へと向かった。最初の一週間は後輩たちの夏合宿の面倒を見て、それが終わってからもOB連中と共に周辺の山々を好き勝手に登っていたから、合わせて二週間ほど山の中にいたことになる。それは今からふり返ってみても、梅雨明け直後の好天がずっと続いた二週間だった。
当時の気象観測データについて、本当は上高地のデータが取れればいいのだが、それがないので松本の気象観測データを近似値として使うことにすると、この1977年の梅雨明け前後は以下のように再現することができる。

これを見ると、この年は梅雨明け後に夏型の天気がしっかりと続く、かなりパワフルな夏だったことがわかる。7月21日から8月の上旬まで、私たちが穂高の山の中で過ごした二週間は、ちょうどスッポリとこの晴天の期間に入っていたのだ。確かに、途中で雨らしきものがあった日は1日だけだったと思う。
後輩たちの夏合宿が終わり、山に残るのは私たちOBだけになってから、「山三昧」の日々の中で、旧友のT君と私は岳沢から少し「遠征」に出てみようと、槍ヶ岳まで行ってみることにした。ツェルト(簡易テント)一つを持って、初日はゆっくり出て穂高岳山荘のそばに幕営し、翌朝は早くから槍を目指した。北穂高岳から飛騨側がスッパリと切れ落ちた「飛騨泣き」を下って「大キレット」の底に降り、そこから大きく登り返して南岳へ。そして目標の槍ヶ岳に到達すると、あとは槍沢をひたすら下り、梓川に沿って上高地まで。

一日の行程が、沿面距離にして26キロ。累計の高度差は上りが1500m、下りが2900mという道のりで、槍沢を下りきったあたりで夕方近くになってしまった。それよりも何よりも、長い距離を歩いてさすがに体がエネルギー切れを起こしてしまい、足に力が入らない。当時の山岳部の伝統で私たちは自炊主義だったのだが、この時ばかりはそうもいかず、徳沢園に着いた時に山小屋で一杯の蕎麦を食べて、何とか元気を取り戻したものだった。上高地の小梨平キャンプ場に着いたのは、夜も9時に近い頃だっただろうか。今思い出してみても、よくもまあ毎日毎日山ばかりやっていたものである。
この年のようにパワフルな梅雨明けもあれば、梅雨明け宣言が出た後は冴えない夏になった年もある。後者の代表例は昨年(2011年)の夏だろう。梅雨明け宣言の前までは晴れて暑い日が続いていたのに、梅雨明けが宣言された途端、皮肉なことに梅雨の戻りのようになってしまった。そこから8月の上旬にかけて、本来なら夏山のベスト・シーズンにあたる時期なのだが、冴えない天気ばかりでアテが外れた登山者も多かったのではないだろうか。(私は8/6~8/8の日程で、あの懐かしい岳沢を再訪したのだが、晴れの日でも毎日昼過ぎから激しい雷雨になる、ちょっと不思議な天候だった。)

もっとも、昨年は東日本大震災に伴う原発事故の影響で、私たちはかつてない規模の節電を余儀なくされていたから、「失速した夏」も結果的には都合が良かったのかもしれない。
さて、今年も梅雨が明けた。とりあえずは猛暑日が続いているが、この先はどんな真夏になるのだろう。何も考えないでよかった学生時代とは異なり、この夏は仕事もなかなか気を抜けないし、家族のこともあるので、休みを取って高い山を目指すのも一回出来るかどうかというのが現状ではあるが、暑い夏はせっせと汗をかいて、元気に過ごしていきたいと思う。
今年を含めて、21世紀に入ってからの12年間の記録から平均値を割り出してみると、関東甲信地方では梅雨入りが6月7日、梅雨明けが7月19日、従って梅雨の期間は42日間というのが相場であるようだ。それに対して今年は梅雨入りが6月9日、明けが7月17日、期間は38日間だったから、タイミングといい長さといい極めて平均的な梅雨だったと言えるかもしれない。

(関東甲信地方の梅雨入りと梅雨明け)
もっとも、梅雨の期間中には必ず日本のどこかが大雨による被害に遭っている。昨年はそれが新潟・福島両県の県境あたりだった。(おかげでJR只見線には未だに復旧していない箇所がある。)そして今年は、何といっても九州北部の豪雨だろう。久留米に住む友人が先週末に写真付きのメールを送ってくれたのだが、巨大な濁流となった筑後川の画像には実に生々しいものがあった。
話は40年以上前にさかのぼる。
人類が地球以外の星に初めて足跡を残した、米アポロ11号の月面着陸。それは1969(昭和44)年の、日本時間では7月21日の早朝の出来事だったのだが、当時私は中学一年生で、その日は夏の臨海学校で千葉の富浦へ合宿に行っていたから、テレビでリアルタイムにそのニュースを見るような機会はなかった。
調べてみると、この年の関東甲信地方の梅雨明けは7月14日だから、私たちが富浦の海で泳ぎ、宇宙の彼方で人類が初めて月に降り立ったのは、その梅雨明けから一週間ほど経った頃のことになる。一般に、梅雨明け後の十日間ほどは夏型の天候が安定すると言われるが、確かに私の中に残るこの時の臨海学校の思い出は、来る日も来る日も青い空と白い雲、穏やかな内房の海、そしてみんな真っ黒になって東京へ帰って来たこと、といったところだろうか。
太平洋高気圧の勢力が強くなって梅雨前線が北へ押し上げられる、その時に前線が通過する場所では強い雨が降ることが多い。子供の頃は、梅雨の終わりといえば激しい雷雨があったりして(大体それは夜だった)、それが止むと一転して太陽が照りつける夏空がやって来た。梅雨というのは、そんな風にかなり明快に明けたものだった。
アポロ・イレブンの年から8年が経った1977(昭和52)年の夏、私は大学生になっていて、久しぶりにビッグな夏休みを迎えることになった。その年の関東甲信地方の梅雨明けは7月21日。私たちは、その梅雨明けを待っていたかのように、ザックを担いで穂高の岳沢へと向かった。最初の一週間は後輩たちの夏合宿の面倒を見て、それが終わってからもOB連中と共に周辺の山々を好き勝手に登っていたから、合わせて二週間ほど山の中にいたことになる。それは今からふり返ってみても、梅雨明け直後の好天がずっと続いた二週間だった。
当時の気象観測データについて、本当は上高地のデータが取れればいいのだが、それがないので松本の気象観測データを近似値として使うことにすると、この1977年の梅雨明け前後は以下のように再現することができる。

これを見ると、この年は梅雨明け後に夏型の天気がしっかりと続く、かなりパワフルな夏だったことがわかる。7月21日から8月の上旬まで、私たちが穂高の山の中で過ごした二週間は、ちょうどスッポリとこの晴天の期間に入っていたのだ。確かに、途中で雨らしきものがあった日は1日だけだったと思う。
後輩たちの夏合宿が終わり、山に残るのは私たちOBだけになってから、「山三昧」の日々の中で、旧友のT君と私は岳沢から少し「遠征」に出てみようと、槍ヶ岳まで行ってみることにした。ツェルト(簡易テント)一つを持って、初日はゆっくり出て穂高岳山荘のそばに幕営し、翌朝は早くから槍を目指した。北穂高岳から飛騨側がスッパリと切れ落ちた「飛騨泣き」を下って「大キレット」の底に降り、そこから大きく登り返して南岳へ。そして目標の槍ヶ岳に到達すると、あとは槍沢をひたすら下り、梓川に沿って上高地まで。

一日の行程が、沿面距離にして26キロ。累計の高度差は上りが1500m、下りが2900mという道のりで、槍沢を下りきったあたりで夕方近くになってしまった。それよりも何よりも、長い距離を歩いてさすがに体がエネルギー切れを起こしてしまい、足に力が入らない。当時の山岳部の伝統で私たちは自炊主義だったのだが、この時ばかりはそうもいかず、徳沢園に着いた時に山小屋で一杯の蕎麦を食べて、何とか元気を取り戻したものだった。上高地の小梨平キャンプ場に着いたのは、夜も9時に近い頃だっただろうか。今思い出してみても、よくもまあ毎日毎日山ばかりやっていたものである。
この年のようにパワフルな梅雨明けもあれば、梅雨明け宣言が出た後は冴えない夏になった年もある。後者の代表例は昨年(2011年)の夏だろう。梅雨明け宣言の前までは晴れて暑い日が続いていたのに、梅雨明けが宣言された途端、皮肉なことに梅雨の戻りのようになってしまった。そこから8月の上旬にかけて、本来なら夏山のベスト・シーズンにあたる時期なのだが、冴えない天気ばかりでアテが外れた登山者も多かったのではないだろうか。(私は8/6~8/8の日程で、あの懐かしい岳沢を再訪したのだが、晴れの日でも毎日昼過ぎから激しい雷雨になる、ちょっと不思議な天候だった。)

もっとも、昨年は東日本大震災に伴う原発事故の影響で、私たちはかつてない規模の節電を余儀なくされていたから、「失速した夏」も結果的には都合が良かったのかもしれない。
さて、今年も梅雨が明けた。とりあえずは猛暑日が続いているが、この先はどんな真夏になるのだろう。何も考えないでよかった学生時代とは異なり、この夏は仕事もなかなか気を抜けないし、家族のこともあるので、休みを取って高い山を目指すのも一回出来るかどうかというのが現状ではあるが、暑い夏はせっせと汗をかいて、元気に過ごしていきたいと思う。
森の緑、空の青 [季節]
日曜日の朝は、明るい光の下にあった。
朝7時起床。前夜は飲み会で遅くなり6時間も寝ていないが、窓の外からこぼれてくる朝の光を感じて、体内時計のスイッチが入ってしまったようだ。天気予報には曇や雨マークがついていたはずだが、ベランダに出てみると外は青空である。昨日は関東甲信地方の「梅雨入り」が発表された。だが、えてしてそんなもので、その翌日は早速梅雨の中休みのようである。ならば、今日は少し体を動かすことにしようか。
日曜日だから、家族が起き出してくるのはもっと遅い。家内と近所で朝の買い出しを済ませ、一家でのんびりと朝食をとった後、私はウォーキングに出かけることにした。まだ朝の10時台だから、外を照らす太陽は元気である。そして、街路樹の緑がきれいだ。

歩き始めて約20分。白山下の交差点から坂道を少し上がると、白山神社の境内に。恒例の「あじさい祭り」が昨日から始まっている。お祭りが目当てではないが、私は毎年この時期にここを訪れてきた。そのたびに、紫陽花といっても実に様々な種類があることを知らされる。雨に濡れた淡い色の花が代表的なイメージだが、明るい太陽を浴びた紫陽花もいいものだ。

白山神社をあとに、白山上から本郷通りへ。真っ直ぐに歩き続けてJR駒込駅を過ぎる。本郷通りはその先の霜降橋という交差点が谷底になっていて、そこを横切る道路は駒込駅の東側をくぐって上野の谷中の方面へと続いている。これが谷田川という河川の跡らしいのだが、確かにこのあたりの地形には微妙な凹凸があって、都市化が進む前の元々の自然の地形はどんな風だったのだろうかと想像しながら歩くのも、面白いものである。
坂道を登ってT字路を左に曲れば、今はバラの庭が見頃の旧古河庭園。今日は好天とあって、あちこちから入場者が集まって来る。坂の上に洋館、その下に各種のバラが咲く洋式庭園、そして一番低い場所には日本庭園。元々は陸奥宗光の別邸だったのが、彼の子息が古河財閥に婿入りし、古河家のものになったという。日中戦争の時代にはあの汪兆銘がかくまわれていた、という説もあるこの洋館。設計にたずさわった英国人のJ・コンドル博士は、湯島の岩崎邸や鹿鳴館などの設計者でもあったそうだ。ここも、私が毎年一度は足を運ぶ場所の一つである。



旧古河庭園から15分も歩けば、王子の飛鳥山。ちょっとした丘になっていて、緑が深い。八代将軍・吉宗の時代に桜が植えられたことで、後世には花見の名所となった。今も都内有数の緑地である。東側の斜面の下、JRの線路との間には数多くのアジサイが花を開いていて、これもこの時期の風物詩である。

飛鳥山の一帯は、ちょっと不思議な地形をしている。顕著な丘が二つあり、その間の谷を現在の明治通りが走っていて、都電荒川線の電車がウンウン言いながら急な坂道を上がっていく。その坂道の地下を暗渠で流れているが石神井川。東京の西部から流れて来て、ここから北東へ1kmほどの地点で隅田川に合流している。昭和33年の狩野川台風の時は、まだ暗渠になっていなかったこの場所で石神井川が氾濫し、飛鳥山の東側の低地部分にある王子の駅が水に浸かったそうである。
その石神井川は、両岸に遊歩道が整備されている。せっかくだから、王子から川に沿って歩いてみよう。桜並木の緑が続き、両岸はコンクリートの垂直な壁になっていて、思ったよりも深い谷だ。川はかなり低いところを流れている。途中に自然の地形を利用したと思われる大きな遊水地が設けられていて、石神井川はそれなりにスケールの大きな川だったことを知らされる。


このあたりでは川の名前もかつては滝野川と呼ばれたという。北区滝野川という町名にそれが残されているが、江戸時代の錦絵を見ると、かなり深い渓谷として描かれている。錦絵だから多分にデフォルメはあったとしても、その川の名前が示すように、あちこちに滝のような急流がある川だったのかもしれない。
王子から速足で20分ほども歩けば、板橋・十条間で埼京線の線路をくぐる。印象としては、このあたりの谷と緑が最も深いように思われた。

埼京線の西側に出ると、その先は長い。帝京大学の建物などを見ながら、川が中山道と交差する地点まで歩くと、結構な距離だ。今日の石神井川遡行はそこまでにして、私は中山道を少し戻り、東武東上線の大山駅まで歩いて、今日のウォーキングをしめくくることにした。測ってみれば12kmちょうど。歩行時間も3時間ちょうど。青空を眺め、緑の中をたっぷり歩いた、心地よい日曜日だった。
「私は、人間は青という色に特別な思いを抱いてきたと思います。人間にとって最も身近な青は空の青、あるいは森の緑ですよね。人がなぜそれらを美しく感じるかといえば、そこに行けば生き延びられるからです。つまり、美とは生き延びるための本能、生きる知恵そのものだと思うんです。」
(「空や水の『青さ』を求めるのは生物の本能だ。」 千住博×福岡伸一 “Fore” 2012年6月号)

朝7時起床。前夜は飲み会で遅くなり6時間も寝ていないが、窓の外からこぼれてくる朝の光を感じて、体内時計のスイッチが入ってしまったようだ。天気予報には曇や雨マークがついていたはずだが、ベランダに出てみると外は青空である。昨日は関東甲信地方の「梅雨入り」が発表された。だが、えてしてそんなもので、その翌日は早速梅雨の中休みのようである。ならば、今日は少し体を動かすことにしようか。
日曜日だから、家族が起き出してくるのはもっと遅い。家内と近所で朝の買い出しを済ませ、一家でのんびりと朝食をとった後、私はウォーキングに出かけることにした。まだ朝の10時台だから、外を照らす太陽は元気である。そして、街路樹の緑がきれいだ。

歩き始めて約20分。白山下の交差点から坂道を少し上がると、白山神社の境内に。恒例の「あじさい祭り」が昨日から始まっている。お祭りが目当てではないが、私は毎年この時期にここを訪れてきた。そのたびに、紫陽花といっても実に様々な種類があることを知らされる。雨に濡れた淡い色の花が代表的なイメージだが、明るい太陽を浴びた紫陽花もいいものだ。
白山神社をあとに、白山上から本郷通りへ。真っ直ぐに歩き続けてJR駒込駅を過ぎる。本郷通りはその先の霜降橋という交差点が谷底になっていて、そこを横切る道路は駒込駅の東側をくぐって上野の谷中の方面へと続いている。これが谷田川という河川の跡らしいのだが、確かにこのあたりの地形には微妙な凹凸があって、都市化が進む前の元々の自然の地形はどんな風だったのだろうかと想像しながら歩くのも、面白いものである。
坂道を登ってT字路を左に曲れば、今はバラの庭が見頃の旧古河庭園。今日は好天とあって、あちこちから入場者が集まって来る。坂の上に洋館、その下に各種のバラが咲く洋式庭園、そして一番低い場所には日本庭園。元々は陸奥宗光の別邸だったのが、彼の子息が古河財閥に婿入りし、古河家のものになったという。日中戦争の時代にはあの汪兆銘がかくまわれていた、という説もあるこの洋館。設計にたずさわった英国人のJ・コンドル博士は、湯島の岩崎邸や鹿鳴館などの設計者でもあったそうだ。ここも、私が毎年一度は足を運ぶ場所の一つである。

旧古河庭園から15分も歩けば、王子の飛鳥山。ちょっとした丘になっていて、緑が深い。八代将軍・吉宗の時代に桜が植えられたことで、後世には花見の名所となった。今も都内有数の緑地である。東側の斜面の下、JRの線路との間には数多くのアジサイが花を開いていて、これもこの時期の風物詩である。
飛鳥山の一帯は、ちょっと不思議な地形をしている。顕著な丘が二つあり、その間の谷を現在の明治通りが走っていて、都電荒川線の電車がウンウン言いながら急な坂道を上がっていく。その坂道の地下を暗渠で流れているが石神井川。東京の西部から流れて来て、ここから北東へ1kmほどの地点で隅田川に合流している。昭和33年の狩野川台風の時は、まだ暗渠になっていなかったこの場所で石神井川が氾濫し、飛鳥山の東側の低地部分にある王子の駅が水に浸かったそうである。
その石神井川は、両岸に遊歩道が整備されている。せっかくだから、王子から川に沿って歩いてみよう。桜並木の緑が続き、両岸はコンクリートの垂直な壁になっていて、思ったよりも深い谷だ。川はかなり低いところを流れている。途中に自然の地形を利用したと思われる大きな遊水地が設けられていて、石神井川はそれなりにスケールの大きな川だったことを知らされる。
このあたりでは川の名前もかつては滝野川と呼ばれたという。北区滝野川という町名にそれが残されているが、江戸時代の錦絵を見ると、かなり深い渓谷として描かれている。錦絵だから多分にデフォルメはあったとしても、その川の名前が示すように、あちこちに滝のような急流がある川だったのかもしれない。
王子から速足で20分ほども歩けば、板橋・十条間で埼京線の線路をくぐる。印象としては、このあたりの谷と緑が最も深いように思われた。
埼京線の西側に出ると、その先は長い。帝京大学の建物などを見ながら、川が中山道と交差する地点まで歩くと、結構な距離だ。今日の石神井川遡行はそこまでにして、私は中山道を少し戻り、東武東上線の大山駅まで歩いて、今日のウォーキングをしめくくることにした。測ってみれば12kmちょうど。歩行時間も3時間ちょうど。青空を眺め、緑の中をたっぷり歩いた、心地よい日曜日だった。
「私は、人間は青という色に特別な思いを抱いてきたと思います。人間にとって最も身近な青は空の青、あるいは森の緑ですよね。人がなぜそれらを美しく感じるかといえば、そこに行けば生き延びられるからです。つまり、美とは生き延びるための本能、生きる知恵そのものだと思うんです。」
(「空や水の『青さ』を求めるのは生物の本能だ。」 千住博×福岡伸一 “Fore” 2012年6月号)
小さきものたちへ [季節]
5月も第三週に入り、夜が明けるのが早くなった。
私は朝の光を体に受けて目覚めていく感覚が好きなので、寝室のカーテンを閉め切ってしまう習慣がない。窓の半分ぐらいはカーテンで遮らないようにしているので、東の空がある程度の明るさになると体内時計のスイッチが入り始めるようだ。(だから、今はずいぶんと早起きになるが、真冬は目覚めるのが一時間ぐらい遅くなる。)
今朝も5時少し前に目が覚めてしまった。東京の日の出は4時35分だから、もう外は十分に明るい。ベランダへ出て、まずは深呼吸。そして植木に水をやり、外の緑を眺めることにする。天気予報によれば、今日の日中は夏の暑さになるそうだが、眼下の桜並木の緑陰を吹き抜ける早朝の風は実に爽やかだ。
薫風自南来 (薫風南より来たり) 殿閣生微涼 (殿閣微涼を生ず)
蘇東坡の有名なこの句には、本当は当時の政治に係わる文脈が色々あるそうなのだが、そういうことは抜きに、一つの禅語として使われることも多い。そして、その方が私は好きだ。
「初夏になると、青葉の香りを含んだ風が南の方から吹いてきて、宮殿の中の隅々までが涼しげな空気に包まれる」
ぐらいの意味だろうか。薫風がもたらす涼しさ、爽やかさの中に、物事にとらわれず煩悩を取り払った無心の境地を見ているのだろう。それは、日本人の季節感にも寄り添うものと言える。
吹く風は爽やかで淡々としているが、この季節、我家のベランダは一年で一番賑やかになる。それも、主人公は小さな新しい命ばかりだ。
爽やかな緑の葉と清楚な白い花のシンプルな組み合わせが私のお気に入りでもあるヒメウツギ。今年は開花が例年より少し遅れて4月の終わり頃になったが、花が咲き誇る時期は意外に短くて、今日のような薫風が吹けばそろそろ終わりになるだろう。

その隣で新たな葉を盛んに繁らせているのは、カベルネ・ソービニョン種のブドウ。我家のベランダに根を張ってから3回目のシーズンになった。去年延びた枝を2月の初めに剪定したのだが、春が来ると新しい枝を幾つも伸ばし、驚くほどのスピードで葉を繁らせていく。そして、ブドウの房の赤ん坊が今年も姿を見せた。これから一夏をかけてどんな風に成長していくか、今から楽しみなことだ。

カベルネ・ソービニョン種のブドウは葉の切れ込みが大きいのだが、それとは対照的に若葉には大きな切れ込みのないのが、ピノ・ノワール種のブドウだ。昨年の夏に会社の同僚から分けてもらったもので、このベランダで冬を越した新たな仲間である。ブルゴーニュの赤ワインに使われる種類のものだが、そのブルゴーニュ地方を離れ、特に海外でピノ・ノワールを育て、優れた赤ワインを作ることはとても難しいことなのだそうだ。私はそんな大それたことは何も考えていない。ただブドウとして育ち、目を楽しませてくれればそれでいいのである。

プランター・ボックスの前でしばし屈みこんでいたが、立ち上がって左を向くと、すっかり明るくなった東の空を背景に、私の目の高さよりも高い位置で何枚かの若葉が輝いている。アボカドの新しい葉である。
果実の真ん中に、ピンポン玉よりも二回りぐらい大きな丸い種のあるアボカド。料理の後に残ったその種を試しにプランター・ボックスの土の中に埋めてみたのが、5年ほど前の5月の連休の頃だった。冷蔵庫で冷やされた種は芽を出さないことが多いと聞いていたので、特に期待もしていなかったのだが、季節が夏を迎えたある日、それが土の中から芽を出していた。それからどんどん大きくなったので独立した一つの鉢に植え替え、今は私の背丈よりも高くなっている。

このアボカド君、中米の原産だから、今頃の季節から夏にかけては実に嬉しそうで、新たな葉をたくさん見せるのだが、反対に寒さには弱い。だから、冬の間は室内に入れてやる必要があるのだが、私よりも背が高くなったぐらいだから、室内で案外場所を取るのが難点ではある。これも、何年待ってもアボカドの実を結ぶことはなさそうだが、そんなことまで期待をしている訳ではない。南の国の植物らしく、濃くて元気な緑をいつも見せてくれていれば、それでいいのである。
再び足元に目を落すと、いつかいつかと待っていたミニバラの蕾が、今朝やっと花弁を開いていた。まだ寒い頃から少し手をかけたことが奏功したのか、今年は蕾の数が多く、その一つ一つが例年よりも大きく、そして花弁の赤色が濃くなった。5月の太陽を浴びて、これから次々に花を開いていくことだろう。

我家の小さなベランダで、競い合うように風薫る5月を謳歌している小さな新しい命の数々。ちょうどそんな季節に、我家の息子と娘は、片や国家試験、片や「就活」という、実社会へと羽ばたいて行くための関門に挑む、今がまさにその真っ最中である。
今年新たに姿を見せたブドウの若葉のように、二人の子供がまだヨチヨチ歩きだったのはそんなに昔のことでもないような気がしてしまうが、その二人もいつの間にかそんな歳になった。それぞれにもう大人なんだから、親として出来ることは限られているのだが、ベランダの小さな命たちに元気をもらいながら、風薫るこの季節を二人が悔いなく生き抜いてくれるよう、彼らの可能性を信じつつ、静かに見守って行きたいと思う。
気がつけば、もう6時になった。家内が起き出してきて、朝食の支度を始めている。
今朝も一家四人、笑顔で食卓を囲むことにしよう。
私は朝の光を体に受けて目覚めていく感覚が好きなので、寝室のカーテンを閉め切ってしまう習慣がない。窓の半分ぐらいはカーテンで遮らないようにしているので、東の空がある程度の明るさになると体内時計のスイッチが入り始めるようだ。(だから、今はずいぶんと早起きになるが、真冬は目覚めるのが一時間ぐらい遅くなる。)
今朝も5時少し前に目が覚めてしまった。東京の日の出は4時35分だから、もう外は十分に明るい。ベランダへ出て、まずは深呼吸。そして植木に水をやり、外の緑を眺めることにする。天気予報によれば、今日の日中は夏の暑さになるそうだが、眼下の桜並木の緑陰を吹き抜ける早朝の風は実に爽やかだ。
薫風自南来 (薫風南より来たり) 殿閣生微涼 (殿閣微涼を生ず)
蘇東坡の有名なこの句には、本当は当時の政治に係わる文脈が色々あるそうなのだが、そういうことは抜きに、一つの禅語として使われることも多い。そして、その方が私は好きだ。
「初夏になると、青葉の香りを含んだ風が南の方から吹いてきて、宮殿の中の隅々までが涼しげな空気に包まれる」
ぐらいの意味だろうか。薫風がもたらす涼しさ、爽やかさの中に、物事にとらわれず煩悩を取り払った無心の境地を見ているのだろう。それは、日本人の季節感にも寄り添うものと言える。
吹く風は爽やかで淡々としているが、この季節、我家のベランダは一年で一番賑やかになる。それも、主人公は小さな新しい命ばかりだ。
爽やかな緑の葉と清楚な白い花のシンプルな組み合わせが私のお気に入りでもあるヒメウツギ。今年は開花が例年より少し遅れて4月の終わり頃になったが、花が咲き誇る時期は意外に短くて、今日のような薫風が吹けばそろそろ終わりになるだろう。
その隣で新たな葉を盛んに繁らせているのは、カベルネ・ソービニョン種のブドウ。我家のベランダに根を張ってから3回目のシーズンになった。去年延びた枝を2月の初めに剪定したのだが、春が来ると新しい枝を幾つも伸ばし、驚くほどのスピードで葉を繁らせていく。そして、ブドウの房の赤ん坊が今年も姿を見せた。これから一夏をかけてどんな風に成長していくか、今から楽しみなことだ。
カベルネ・ソービニョン種のブドウは葉の切れ込みが大きいのだが、それとは対照的に若葉には大きな切れ込みのないのが、ピノ・ノワール種のブドウだ。昨年の夏に会社の同僚から分けてもらったもので、このベランダで冬を越した新たな仲間である。ブルゴーニュの赤ワインに使われる種類のものだが、そのブルゴーニュ地方を離れ、特に海外でピノ・ノワールを育て、優れた赤ワインを作ることはとても難しいことなのだそうだ。私はそんな大それたことは何も考えていない。ただブドウとして育ち、目を楽しませてくれればそれでいいのである。
プランター・ボックスの前でしばし屈みこんでいたが、立ち上がって左を向くと、すっかり明るくなった東の空を背景に、私の目の高さよりも高い位置で何枚かの若葉が輝いている。アボカドの新しい葉である。
果実の真ん中に、ピンポン玉よりも二回りぐらい大きな丸い種のあるアボカド。料理の後に残ったその種を試しにプランター・ボックスの土の中に埋めてみたのが、5年ほど前の5月の連休の頃だった。冷蔵庫で冷やされた種は芽を出さないことが多いと聞いていたので、特に期待もしていなかったのだが、季節が夏を迎えたある日、それが土の中から芽を出していた。それからどんどん大きくなったので独立した一つの鉢に植え替え、今は私の背丈よりも高くなっている。
このアボカド君、中米の原産だから、今頃の季節から夏にかけては実に嬉しそうで、新たな葉をたくさん見せるのだが、反対に寒さには弱い。だから、冬の間は室内に入れてやる必要があるのだが、私よりも背が高くなったぐらいだから、室内で案外場所を取るのが難点ではある。これも、何年待ってもアボカドの実を結ぶことはなさそうだが、そんなことまで期待をしている訳ではない。南の国の植物らしく、濃くて元気な緑をいつも見せてくれていれば、それでいいのである。
再び足元に目を落すと、いつかいつかと待っていたミニバラの蕾が、今朝やっと花弁を開いていた。まだ寒い頃から少し手をかけたことが奏功したのか、今年は蕾の数が多く、その一つ一つが例年よりも大きく、そして花弁の赤色が濃くなった。5月の太陽を浴びて、これから次々に花を開いていくことだろう。
我家の小さなベランダで、競い合うように風薫る5月を謳歌している小さな新しい命の数々。ちょうどそんな季節に、我家の息子と娘は、片や国家試験、片や「就活」という、実社会へと羽ばたいて行くための関門に挑む、今がまさにその真っ最中である。
今年新たに姿を見せたブドウの若葉のように、二人の子供がまだヨチヨチ歩きだったのはそんなに昔のことでもないような気がしてしまうが、その二人もいつの間にかそんな歳になった。それぞれにもう大人なんだから、親として出来ることは限られているのだが、ベランダの小さな命たちに元気をもらいながら、風薫るこの季節を二人が悔いなく生き抜いてくれるよう、彼らの可能性を信じつつ、静かに見守って行きたいと思う。
気がつけば、もう6時になった。家内が起き出してきて、朝食の支度を始めている。
今朝も一家四人、笑顔で食卓を囲むことにしよう。
山の常識 [季節]
5月5日、土曜日。「子供の日」の東京は朝から素晴らしい快晴になった。今朝は窓の外の緑が一段と眩しい。こんなにきれいな青空が広がるのは、先週の日曜日以来のことだ。
こうなると、時間を無駄にしてはいられない。私は朝5時には目が覚めていたので、6時半頃から10kmのジョギングに出かけたのをはじめとして、午前中にセカセカと色々なことをした。要するに、天気の良い休日は室内でじっとしていられない性格なのである。
ベランダの植物を相手に一仕事が終わり、昼前になると、家内と娘が予定通り出かける仕度を始めていた。今日はこれからランチボックスとワインを持って三人で都心の公園へ出かけ、芝生の上で青空と緑を楽しむことにしていたのである。

メトロに乗って家から45分ほど。芝生の上を好きなように歩けるその公園には既に大勢の人出があったが、何しろ広い園内だから場所に困ることもない。私たちは桜の木陰にシートを広げ、ランチボックスを開いた。そして乾杯。たとえプラスチックのカップでも、太陽と緑の下で楽しむ赤ワインはいいものだ。
例年、5月の連休は遠出をしないことにしている。限りのある時間の中で道路の渋滞に巻き込まれるのは馬鹿げているし、行った先々も混雑ばかりなのだとすると、とても時間とエネルギーを費やす気になれないのだ。むしろ、近場でさっと楽しめることをする方がいい。そんな訳で、「昭和の日」の日曜日は山仲間たちと、電車と路線バスを使って比較的早い時間に帰って来られる半日の山歩きを企画。そして、連休の後半は家族と共に身近な所で時間を過ごそうと決めていた。

それにしても、大型連休の後半は天気が荒れた。
その荒天のために北アルプスで登山者の遭難が相次ぎ、5月4日だけでも白馬岳(2932m)付近で6人、爺ヶ岳(2670m)と涸沢岳(3110m)付近でそれぞれ1人が命を落とした。計8人はいずれも60代以上で、内4人は70代だったという。天候の急変で吹雪に巻き込まれ、低体温症に陥ったというのが8人に共通している。
5月3日(木)は天気が悪い。天気予報は早くからそう告げていた。その一方で4日(金)は「曇時々晴」というような予報だった。4日に入山した人たちは、それを当て込んでいたのだろうか。だが、実際には2日(水)17時の予報で4日は「曇一時雨」に変わっていた。この時期の天候はなかなか難しいのである。
.jpg)
「曇時々晴」が「曇一時雨」に変わったという程度なら、「山へ行くのだから多少の雨はもとより覚悟」という御仁は動じないかもしれない。5日(土)には高気圧がやってきて晴れる、そうだとすれば4日は、雨が残ったとしても気圧の谷が過ぎて天候が回復していく過程にあるのだろうと、そう思った人も少なくないことだろう。
だが、「4日は上空に寒気が入ってきて大気の状態が不安定になる」という情報が視覚的にもっと行きわたっていたら、行動を見合わせた人が増えたことにはならなかっただろうか。
今はこれほどの情報化社会。山に向かう電車の中で、スマートフォンを使ってインターネット上の最新の、それも地域をピンポイントに選んだスポット天気予報を確認することが出来る。ラジオで一日三回の気象通報を聞いて、自分で天気図を書くしかなかった私たちの学生時代に比べれば、それは夢のようなことだ。
だが、ネット上の一般向けの天気予報は相変わらず地表付近の天気図ばかりで、テレビの天気予報で時々解説される高層天気図、上空の気温の状況の解説などは見ることが出来ない。確かに高層天気図を理解するためには相応の知識が必要なのだが、地表付近の天気図だけでは読み取れない、けれども実際の天候を左右するようなファクターについては、平易に噛み砕いて一般向けにも情報を提供していくような、便利な時代になったからこそ出来る工夫をもっとしてみる必要がないだろうか。
.jpg)
(一般向けには、こうした画像にも解説が欲しいところだ。)
もちろん、山の遭難事故を天気予報のせいにすることは出来ない。それどころか、8人が命を落とした今回の事故は天気予報以前の、登山のイロハの問題だ。亡くなってしまった方々を今さら批判してみても仕方がないが、やはり山を甘く見ていたとしか言いようがないだろう。5月の連休の頃に標高2500mを超える山では、天候が悪化すれば冬山と同じような条件になる。山に入る以上はそれに備えることが基本中の基本なのだから、フリースさえ持っていなかったというのでは話にならない。
メンバーの中には登山歴の長いベテランもいたという。だが、最近の山の事故で気になるのは、その「ベテラン」といいう言葉が持つ本当の意味だ。登山回数や年数が長ければベテランなのだろうか。四季を通じて安全に山へ行くための基礎を、本当の先達からきちんと学んできた人たちなのだろうか。
一般論として、中高年になってから「見よう見まね」で登山を始めた人でも、場数を踏んで結果的に事故なく10年も山行を続けたら、「山のベテラン」と呼ばれるようになるかもしれない。そして、山行を重ねて山の面白さを経験してしまうと、人生の残り時間から逆算して、元気なうちにあちこちへと精力的に出かけようとするのかもしれない。仲間に触発されて、「彼でも登れたんだから私も」となるケースもあることだろう。
そのことを必ずしも否定するものではないし、人生を意欲的に生きるのは結構なことだが、基本を知らずに山へ行こうとすると、越えてはいけない一線がどこにあるのかがおそらく解らないのだろう。悪天候が予想される時は「行かない勇気」が「行く勇気」に勝ることも。
今回は北アルプスでの5月4日の遭難事故が目立ったが、報道されずとも似たような状況に陥った登山者が他にも少なからずいたのではないだろうか。
5月2日の夜から3日にかけて、関東・東海地方では記録的な大雨になった。この間、24時間の降水量では天城山(静岡)の649ミリが観測史上第1位だったことをはじめとして、箱根(349ミリ)、奥日光(217ミリ)、秩父(138ミリ)、東京(152ミリ)など、各地で一日の降水量の最大値を更新した。丹沢湖では2日と3日で計175ミリの雨が降り、これは平年の5月一ヶ月分の降水量(185ミリ)に匹敵する量だった。
.jpg)
(記録的な大雨が降った5月3日)
これは後講釈で言っているのではない。3日の大雨の状況は日中から度々報道されていたし、アメダスの1時間毎の気象観測データは気象庁のHP上で刻々と更新される。あの日がどれほど記録的な大雨だったのかを、かなりの程度リアルタイムに状況を把握することは、誰にもできたはずである。
山でこんな大雨が降れば、山道が荒れる以上に沢の増水が尋常ではないはずだし、それは雨が止んだからすぐに収まるというものでもないはずだ。付近の林道では土砂崩れだってあるかもしれない。たとえ5月4日に天候が回復していたとしても(実際にはそうならなかったのだが)、そんな大雨が降った翌日はまだ山に近付かないのが常識というものだろう。どんなに山へ行きたくても迷いなくそういう判断が出来ることが、「山のベテラン」の証なのではないだろうか。
中高年層を中心として、山を甘く見たこと、基本を知らずに山へ向かったことによる遭難事故は、これからも続くことだろう。社会人だから山へ行ける時間が限られている、という事情はあるにしても、社会人だからこそ、自分の体は自分一人のものではないはずだ。そして、街中の運動場でスポーツをしていて怪我をするのとは異なり、山でひとたび遭難事故を起こせば、社会のあちこちに多大な迷惑をかけてしまう。それは「武勇伝」ではすまされないことだ。
素晴らしい快晴が一日続いた5月5日、家族と共に都心の新緑を満喫しながら、心の片隅ではこんなことを考えていた。残りの人生、私もあと何年山歩きを続けられるかわからない。状況が許せば登ってみたい山もまだ数多く残っているが、それが全部はかなうべくもない。そこは強欲にならず、若い頃に山岳部の諸先輩から叩き込まれたことをしっかりと守って行きたいと思う。

次回はいつ、山へ行くことになるだろうか。
こうなると、時間を無駄にしてはいられない。私は朝5時には目が覚めていたので、6時半頃から10kmのジョギングに出かけたのをはじめとして、午前中にセカセカと色々なことをした。要するに、天気の良い休日は室内でじっとしていられない性格なのである。
ベランダの植物を相手に一仕事が終わり、昼前になると、家内と娘が予定通り出かける仕度を始めていた。今日はこれからランチボックスとワインを持って三人で都心の公園へ出かけ、芝生の上で青空と緑を楽しむことにしていたのである。
メトロに乗って家から45分ほど。芝生の上を好きなように歩けるその公園には既に大勢の人出があったが、何しろ広い園内だから場所に困ることもない。私たちは桜の木陰にシートを広げ、ランチボックスを開いた。そして乾杯。たとえプラスチックのカップでも、太陽と緑の下で楽しむ赤ワインはいいものだ。
例年、5月の連休は遠出をしないことにしている。限りのある時間の中で道路の渋滞に巻き込まれるのは馬鹿げているし、行った先々も混雑ばかりなのだとすると、とても時間とエネルギーを費やす気になれないのだ。むしろ、近場でさっと楽しめることをする方がいい。そんな訳で、「昭和の日」の日曜日は山仲間たちと、電車と路線バスを使って比較的早い時間に帰って来られる半日の山歩きを企画。そして、連休の後半は家族と共に身近な所で時間を過ごそうと決めていた。
それにしても、大型連休の後半は天気が荒れた。
その荒天のために北アルプスで登山者の遭難が相次ぎ、5月4日だけでも白馬岳(2932m)付近で6人、爺ヶ岳(2670m)と涸沢岳(3110m)付近でそれぞれ1人が命を落とした。計8人はいずれも60代以上で、内4人は70代だったという。天候の急変で吹雪に巻き込まれ、低体温症に陥ったというのが8人に共通している。
5月3日(木)は天気が悪い。天気予報は早くからそう告げていた。その一方で4日(金)は「曇時々晴」というような予報だった。4日に入山した人たちは、それを当て込んでいたのだろうか。だが、実際には2日(水)17時の予報で4日は「曇一時雨」に変わっていた。この時期の天候はなかなか難しいのである。
.jpg)
「曇時々晴」が「曇一時雨」に変わったという程度なら、「山へ行くのだから多少の雨はもとより覚悟」という御仁は動じないかもしれない。5日(土)には高気圧がやってきて晴れる、そうだとすれば4日は、雨が残ったとしても気圧の谷が過ぎて天候が回復していく過程にあるのだろうと、そう思った人も少なくないことだろう。
だが、「4日は上空に寒気が入ってきて大気の状態が不安定になる」という情報が視覚的にもっと行きわたっていたら、行動を見合わせた人が増えたことにはならなかっただろうか。
今はこれほどの情報化社会。山に向かう電車の中で、スマートフォンを使ってインターネット上の最新の、それも地域をピンポイントに選んだスポット天気予報を確認することが出来る。ラジオで一日三回の気象通報を聞いて、自分で天気図を書くしかなかった私たちの学生時代に比べれば、それは夢のようなことだ。
だが、ネット上の一般向けの天気予報は相変わらず地表付近の天気図ばかりで、テレビの天気予報で時々解説される高層天気図、上空の気温の状況の解説などは見ることが出来ない。確かに高層天気図を理解するためには相応の知識が必要なのだが、地表付近の天気図だけでは読み取れない、けれども実際の天候を左右するようなファクターについては、平易に噛み砕いて一般向けにも情報を提供していくような、便利な時代になったからこそ出来る工夫をもっとしてみる必要がないだろうか。
.jpg)
(一般向けには、こうした画像にも解説が欲しいところだ。)
もちろん、山の遭難事故を天気予報のせいにすることは出来ない。それどころか、8人が命を落とした今回の事故は天気予報以前の、登山のイロハの問題だ。亡くなってしまった方々を今さら批判してみても仕方がないが、やはり山を甘く見ていたとしか言いようがないだろう。5月の連休の頃に標高2500mを超える山では、天候が悪化すれば冬山と同じような条件になる。山に入る以上はそれに備えることが基本中の基本なのだから、フリースさえ持っていなかったというのでは話にならない。
メンバーの中には登山歴の長いベテランもいたという。だが、最近の山の事故で気になるのは、その「ベテラン」といいう言葉が持つ本当の意味だ。登山回数や年数が長ければベテランなのだろうか。四季を通じて安全に山へ行くための基礎を、本当の先達からきちんと学んできた人たちなのだろうか。
一般論として、中高年になってから「見よう見まね」で登山を始めた人でも、場数を踏んで結果的に事故なく10年も山行を続けたら、「山のベテラン」と呼ばれるようになるかもしれない。そして、山行を重ねて山の面白さを経験してしまうと、人生の残り時間から逆算して、元気なうちにあちこちへと精力的に出かけようとするのかもしれない。仲間に触発されて、「彼でも登れたんだから私も」となるケースもあることだろう。
そのことを必ずしも否定するものではないし、人生を意欲的に生きるのは結構なことだが、基本を知らずに山へ行こうとすると、越えてはいけない一線がどこにあるのかがおそらく解らないのだろう。悪天候が予想される時は「行かない勇気」が「行く勇気」に勝ることも。
今回は北アルプスでの5月4日の遭難事故が目立ったが、報道されずとも似たような状況に陥った登山者が他にも少なからずいたのではないだろうか。
5月2日の夜から3日にかけて、関東・東海地方では記録的な大雨になった。この間、24時間の降水量では天城山(静岡)の649ミリが観測史上第1位だったことをはじめとして、箱根(349ミリ)、奥日光(217ミリ)、秩父(138ミリ)、東京(152ミリ)など、各地で一日の降水量の最大値を更新した。丹沢湖では2日と3日で計175ミリの雨が降り、これは平年の5月一ヶ月分の降水量(185ミリ)に匹敵する量だった。
.jpg)
(記録的な大雨が降った5月3日)
これは後講釈で言っているのではない。3日の大雨の状況は日中から度々報道されていたし、アメダスの1時間毎の気象観測データは気象庁のHP上で刻々と更新される。あの日がどれほど記録的な大雨だったのかを、かなりの程度リアルタイムに状況を把握することは、誰にもできたはずである。
山でこんな大雨が降れば、山道が荒れる以上に沢の増水が尋常ではないはずだし、それは雨が止んだからすぐに収まるというものでもないはずだ。付近の林道では土砂崩れだってあるかもしれない。たとえ5月4日に天候が回復していたとしても(実際にはそうならなかったのだが)、そんな大雨が降った翌日はまだ山に近付かないのが常識というものだろう。どんなに山へ行きたくても迷いなくそういう判断が出来ることが、「山のベテラン」の証なのではないだろうか。
中高年層を中心として、山を甘く見たこと、基本を知らずに山へ向かったことによる遭難事故は、これからも続くことだろう。社会人だから山へ行ける時間が限られている、という事情はあるにしても、社会人だからこそ、自分の体は自分一人のものではないはずだ。そして、街中の運動場でスポーツをしていて怪我をするのとは異なり、山でひとたび遭難事故を起こせば、社会のあちこちに多大な迷惑をかけてしまう。それは「武勇伝」ではすまされないことだ。
素晴らしい快晴が一日続いた5月5日、家族と共に都心の新緑を満喫しながら、心の片隅ではこんなことを考えていた。残りの人生、私もあと何年山歩きを続けられるかわからない。状況が許せば登ってみたい山もまだ数多く残っているが、それが全部はかなうべくもない。そこは強欲にならず、若い頃に山岳部の諸先輩から叩き込まれたことをしっかりと守って行きたいと思う。
次回はいつ、山へ行くことになるだろうか。
夏が始まる日 [季節]
今年の大型連休では、4月30日(月)が振替休日になった。
29日に山仲間たちと半日山を歩いてきた、その目で改めて眺めてみると、東京の街中も緑が濃くなったものだ。桜並木はいつの間にか立派な緑陰を作っていて、その下を歩くのは花の頃にも増して気分がいい。最近は街路樹に使われることが多くなったハナミズキは今が花の真っ盛りで、その清楚な白が新緑との鮮やかなコントラストを見せている。
今日は日本が振替休日。そして明日の5月1日は世界の多くの国々で祝日である。
かつては労働運動の代名詞のような存在だったのが、今はすっかり色褪せてしまった「メーデー」。社会主義者たちの運動として1889年に結成された「第二インターナショナル」で掲げられた、国際労働運動のための休日、などという受験勉強的な知識はとっくの昔に忘れてしまった。巷でもメーデーが話題になることはもう殆どないと言っていいだろう。
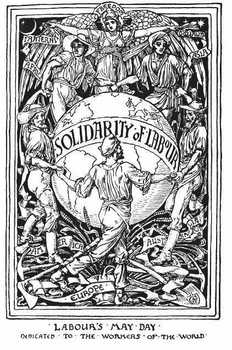
それにしても、万国の労働者が団結してこうした運動を行なう日が、なぜ5月1日だったのか。
それは、北欧や中欧の各国に共通するものとして、遥かな昔からこの日が夏の訪れを祝う日だったことにあるそうだ。
暗くて寒い冬が長く続くヨーロッパでは、春分を過ぎて光がいよいよ明るくなると、人々が活動的になる。古代のケルト人の信仰や北欧神話など、キリスト教が入ってくる以前のヨーロッパの精神世界には、多様な神々や悪魔、死者の魂などが登場するが、それらも人間と同じようにこの季節になると元気になったようだ。
4月30日の夜には生者と死者との境が薄れ、魔女やら死霊やらが集まって大騒ぎをするので、人々はかがり火を焚いてそれらを追い払い、太陽の季節が戻る5月1日を祝ったという。北欧・中欧の各地に共通するそんな風習、それが五月祭(メイフェア)なのだそうだ。夏が始まる日、ということなのだろう。
緯度が北緯50度を越える北国では、地球の公転と共に昼と夜の長さが変わる、その一日当りの変化が低緯度地域よりもずっと大きい。世界各地の日の出・日の入の時刻を計算してくれるインターネット上のサイトを使って、例えば4月30日と5月1日では昼間の時間(日の出から日の入まで)がどれだけ長くなるか、それを調べてみると以下のようになる。(便宜上、いずれも海抜0mとした。)

(駆け足で夏が来るヨーロッパ)
この時期に東京では1日当り1分50秒ずつ昼が長くなるが、北ドイツのハンブルグではそれが3分48秒、スウェーデンのストックホルムでは4分59秒、そして北緯60度に達するフィンランドの首都ヘルシンキでは5分14秒にもなる。つまり、二週間足らずで昼間の時間が一時間も長くなるわけだ。こんなスピードでまっしぐらに夏へと向かうなら、人間誰しも嬉しくなってしまうことだろう。そのフィンランドでは、5月1日は夏至と大晦日に次ぐ大きなお祭りで、前夜から人々は大酒を飲むそうである。
確かに、ヨーロッパの5月は一年で一番いい季節と言っていいだろう。公園も住宅地も花と緑にあふれ、晴れた日に屋外で食事をするのは最高の気分だ。夜もいつまでも明るくなる。1620年に英国南西部のプリマスから新大陸を目指した清教徒たちは、「メイフラワー」という名の船に自らの命運を託したのだが、「希望」という言葉の代名詞になるぐらい、ヨーロッパの5月の花は素晴らしいと、私自身の経験からもそう思う。

一方ドイツでは、4月30日の日没から5月1日の未明までの間、魔女たちがブロッケン山に集まって大宴会を開くという伝承があるそうだ。「ヴァルプルギスの夜」と呼ばれるこの話はゲーテの『ファウスト』にも描かれていて、メフィストフェレスに誘われた主人公がこの宴に酔いしれる場面が第一部に出てくる。
ブロッケン山(標高1141m)は年に300日は霧に覆われ、その霧に登山者の影が映る「ブロッケンの妖怪」が出ることで有名な中部ドイツの山である。『ファウスト』を世に送り出す前の1777年12月、ゲーテ自身が冬期のブロッケン山に登頂を試みている。近代アルピニズムの登場よりもずっと前、まだ山には魔物がいると本気で信じられていた時代のことだ。
ムソルグスキー作曲の交響詩『禿山の一夜』にも、真夜中の山に集まって大騒ぎをする魔物や死霊が登場している。これはロシアの夏至の祭りに因む民話を題材にしているのだそうである。

それらに比べると、日本に住む私たちにとっては、「夏も近づく八十八夜」と歌われては来たものの、5月1日に格別の季節感があるわけでもないし、夏至の頃はたいてい梅雨空だから、一年で一番昼の長い日を祝うという習慣もない。肌感覚として太陽が最も元気なのは7月・8月だ。それらはみな、北欧や中欧に比べて遥かに太陽の光に恵まれた国の季節感。やはり「日ノ本」の国なのである。
その夏至まで、あと一ヶ月と三週間あまり。毎日1分50秒ずつ昼間が長くなるこの時期を、大切に過ごして行きたい。
29日に山仲間たちと半日山を歩いてきた、その目で改めて眺めてみると、東京の街中も緑が濃くなったものだ。桜並木はいつの間にか立派な緑陰を作っていて、その下を歩くのは花の頃にも増して気分がいい。最近は街路樹に使われることが多くなったハナミズキは今が花の真っ盛りで、その清楚な白が新緑との鮮やかなコントラストを見せている。
今日は日本が振替休日。そして明日の5月1日は世界の多くの国々で祝日である。
かつては労働運動の代名詞のような存在だったのが、今はすっかり色褪せてしまった「メーデー」。社会主義者たちの運動として1889年に結成された「第二インターナショナル」で掲げられた、国際労働運動のための休日、などという受験勉強的な知識はとっくの昔に忘れてしまった。巷でもメーデーが話題になることはもう殆どないと言っていいだろう。
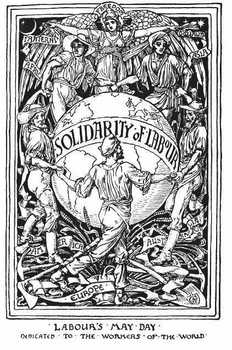
それにしても、万国の労働者が団結してこうした運動を行なう日が、なぜ5月1日だったのか。
それは、北欧や中欧の各国に共通するものとして、遥かな昔からこの日が夏の訪れを祝う日だったことにあるそうだ。
暗くて寒い冬が長く続くヨーロッパでは、春分を過ぎて光がいよいよ明るくなると、人々が活動的になる。古代のケルト人の信仰や北欧神話など、キリスト教が入ってくる以前のヨーロッパの精神世界には、多様な神々や悪魔、死者の魂などが登場するが、それらも人間と同じようにこの季節になると元気になったようだ。
4月30日の夜には生者と死者との境が薄れ、魔女やら死霊やらが集まって大騒ぎをするので、人々はかがり火を焚いてそれらを追い払い、太陽の季節が戻る5月1日を祝ったという。北欧・中欧の各地に共通するそんな風習、それが五月祭(メイフェア)なのだそうだ。夏が始まる日、ということなのだろう。
緯度が北緯50度を越える北国では、地球の公転と共に昼と夜の長さが変わる、その一日当りの変化が低緯度地域よりもずっと大きい。世界各地の日の出・日の入の時刻を計算してくれるインターネット上のサイトを使って、例えば4月30日と5月1日では昼間の時間(日の出から日の入まで)がどれだけ長くなるか、それを調べてみると以下のようになる。(便宜上、いずれも海抜0mとした。)

(駆け足で夏が来るヨーロッパ)
この時期に東京では1日当り1分50秒ずつ昼が長くなるが、北ドイツのハンブルグではそれが3分48秒、スウェーデンのストックホルムでは4分59秒、そして北緯60度に達するフィンランドの首都ヘルシンキでは5分14秒にもなる。つまり、二週間足らずで昼間の時間が一時間も長くなるわけだ。こんなスピードでまっしぐらに夏へと向かうなら、人間誰しも嬉しくなってしまうことだろう。そのフィンランドでは、5月1日は夏至と大晦日に次ぐ大きなお祭りで、前夜から人々は大酒を飲むそうである。
確かに、ヨーロッパの5月は一年で一番いい季節と言っていいだろう。公園も住宅地も花と緑にあふれ、晴れた日に屋外で食事をするのは最高の気分だ。夜もいつまでも明るくなる。1620年に英国南西部のプリマスから新大陸を目指した清教徒たちは、「メイフラワー」という名の船に自らの命運を託したのだが、「希望」という言葉の代名詞になるぐらい、ヨーロッパの5月の花は素晴らしいと、私自身の経験からもそう思う。
一方ドイツでは、4月30日の日没から5月1日の未明までの間、魔女たちがブロッケン山に集まって大宴会を開くという伝承があるそうだ。「ヴァルプルギスの夜」と呼ばれるこの話はゲーテの『ファウスト』にも描かれていて、メフィストフェレスに誘われた主人公がこの宴に酔いしれる場面が第一部に出てくる。
ブロッケン山(標高1141m)は年に300日は霧に覆われ、その霧に登山者の影が映る「ブロッケンの妖怪」が出ることで有名な中部ドイツの山である。『ファウスト』を世に送り出す前の1777年12月、ゲーテ自身が冬期のブロッケン山に登頂を試みている。近代アルピニズムの登場よりもずっと前、まだ山には魔物がいると本気で信じられていた時代のことだ。
ムソルグスキー作曲の交響詩『禿山の一夜』にも、真夜中の山に集まって大騒ぎをする魔物や死霊が登場している。これはロシアの夏至の祭りに因む民話を題材にしているのだそうである。

それらに比べると、日本に住む私たちにとっては、「夏も近づく八十八夜」と歌われては来たものの、5月1日に格別の季節感があるわけでもないし、夏至の頃はたいてい梅雨空だから、一年で一番昼の長い日を祝うという習慣もない。肌感覚として太陽が最も元気なのは7月・8月だ。それらはみな、北欧や中欧に比べて遥かに太陽の光に恵まれた国の季節感。やはり「日ノ本」の国なのである。
その夏至まで、あと一ヶ月と三週間あまり。毎日1分50秒ずつ昼間が長くなるこの時期を、大切に過ごして行きたい。
冬から春へ [季節]
「コーヒーを飲んだら散歩に出ようか。」
窓の外を眺めながら家内とそう話していたのは、午前11時を回った頃だっただろうか。
2月最後の日曜日、前日の天気予報では晴れマークがついていたような気がするが、蓋を開けてみれば寒々とした曇り空が広がっている。目の前の桜並木も、真冬の装いのままだ。各地では梅の開花が大幅に遅れているという。2月も間もなく終わりになるが、春の兆しはまだまだである。
メトロに乗って、都心へと向かう。家内と二人でのんびり散歩というのも、だいぶ久しぶりのことになった。これも寒さが続いたからなのだろう。
東京駅で下りて、八重洲方面を目指す。地下の商店街を長々と歩いて、家内と私は銀座中央通りとの交差点の所で地上に出た。その中央通りを渡れば目的地のブリジストン美術館だ。・・・と思ったら、渡れない。何と今日の中央通りは東京マラソンのコースになっていて、上野方向も銀座方向もランナーたちの列がいつ果てるとなく続いている。(何しろ参加者は3万6千人なのだ!) 通りの反対側へ行くには、日本橋の交差点まで400mぐらい歩き、地下鉄への出入り口を利用するしかない。まぁ、それも一興だろう。家内と私は丸善まで歩き、地下をくぐって道路の東側に出ることにした。
東京マラソンの実物を間近に見たのは、考えてみればこれが初めてなのだが、ランナーたちは皆楽しそうだし、沿道からの声援もなかなか熱い。市民参加型の大イベントとしてもうすっかり定着しているようだ。軍事クーデーターで夜が明けた76年前とは大違いの、賑やかな東京の二・二六。ならば、春は近いか。

だいぶ遠回りをして辿りついたブリジストン美術館では、「パリへ渡った『石橋コレクション』 1962年、春」という展覧会を開催中だった。今からちょうど50年前の1962(昭和36)年にパリ国立近代美術館で、初めて石橋コレクションを紹介する「東京石橋コレクション所蔵-コローからブラックに至るフランス絵画展」が開催された、それを再現してみようという企画である。

日本のコレクターが所蔵するフランスの画家達の作品がパリで展示されるのだから、それらの絵画にとっては「里帰り」になる訳だが、50年前のその絵画展によって、アート・コレクターとしての石橋正二郎の存在は大いに注目を集めたそうだ。
私はいつも、薀蓄を抜きにして絵画を眺めることを楽しむほうだ。どちらかと言えば光が明るくて、色使いが優しく、発想が自由で、眺めているだけでも頭の中が柔らかくなっていくような、そんな絵が好きである。だから、今回並んでいた絵画の中でも、後半部分の作品の方に目が行っていたかな。久しぶりに眺めたピエール・ボナールの明るい風景画や、赤と緑が鮮やかなアンリ・マティスの裸婦像などが印象に強く残った。普段にも増して絵画に明るい光を求めたのは、やはり春が待ち遠しいからか。

絵画展を小一時間楽しみ、外に出てみると、マラソンは銀座方向へと走る列だけになっていた。家内と私は京橋から再びメトロに乗り、表参道へ。ブティック街を通り抜けて根津美術館へと向かう。そこでの展覧会は家内とって今日の一番のお目当て、「虎屋のお雛様」である。
羊羹で有名な和菓子の老舗、「虎屋」。1520年代に京都で創業したというから、殆ど「500年企業」という驚くべき存在である。その虎屋で明治の30年代に、当時の店主が娘の初節句のために集めたり特注したりした雛人形と雛道具の一式が展示されている。ポスターの写真に見る通り、雛壇は実に14段(!)、そこに乗りきらない物も含めて約300点の品々が展示されている。(14段の姿は写真だけで、実際に雛壇に乗せるべき雛道具の一つ一つが、個別に展示されている。)

展示物は江戸期に遡るものから明治時代の作まで様々だが、個々の雛道具はまことに小さなものだ。豆粒ほどの大きさながら、食器や重箱などが極めて精緻に再現されている。なぜここまでのミニチュアをわざわざ作ったのかというと、江戸時代に幕府からたびたび倹約令が出て、雛人形の大きさ(高さ)を制限されたことによるものだという。人形を小さくするなら、道具類もそれに合わせて更に小さく、という訳だが、そういう微細なものを本物と見間違うほど精緻に作ろうとするこだわりが、いかにも日本人のDNAなのだと、改めて思わざるを得ない。遠い祖先の時代から、私たちはこういうことが好きなのである。

京都の風だから、雛人形や道具の飾り方は関東のそれとは異なるところがあり、「あれっ? どっちが左でどっちが右だったっけ?」などと言いながら、家内だけでなく私も結構楽しませてもらうことになった。
雛祭りといえば、いまだ寒い頃ながら、かすかな春の到来を慶ぶ時期である。その3月3日まであと一週間。冬の寒さはまだ続きそうで、一足飛びに春がやって来る訳ではないから、もう少し我慢をしなければならない。今日は、まだ見えぬその春を探すようにして歩く、家内との半日になった。
なお、「虎屋のお雛様」は3月4日になってもあたふたと片付けられてしまう訳ではなく、展覧会は4月8日まで続くようである。
窓の外を眺めながら家内とそう話していたのは、午前11時を回った頃だっただろうか。
2月最後の日曜日、前日の天気予報では晴れマークがついていたような気がするが、蓋を開けてみれば寒々とした曇り空が広がっている。目の前の桜並木も、真冬の装いのままだ。各地では梅の開花が大幅に遅れているという。2月も間もなく終わりになるが、春の兆しはまだまだである。
メトロに乗って、都心へと向かう。家内と二人でのんびり散歩というのも、だいぶ久しぶりのことになった。これも寒さが続いたからなのだろう。
東京駅で下りて、八重洲方面を目指す。地下の商店街を長々と歩いて、家内と私は銀座中央通りとの交差点の所で地上に出た。その中央通りを渡れば目的地のブリジストン美術館だ。・・・と思ったら、渡れない。何と今日の中央通りは東京マラソンのコースになっていて、上野方向も銀座方向もランナーたちの列がいつ果てるとなく続いている。(何しろ参加者は3万6千人なのだ!) 通りの反対側へ行くには、日本橋の交差点まで400mぐらい歩き、地下鉄への出入り口を利用するしかない。まぁ、それも一興だろう。家内と私は丸善まで歩き、地下をくぐって道路の東側に出ることにした。
東京マラソンの実物を間近に見たのは、考えてみればこれが初めてなのだが、ランナーたちは皆楽しそうだし、沿道からの声援もなかなか熱い。市民参加型の大イベントとしてもうすっかり定着しているようだ。軍事クーデーターで夜が明けた76年前とは大違いの、賑やかな東京の二・二六。ならば、春は近いか。

だいぶ遠回りをして辿りついたブリジストン美術館では、「パリへ渡った『石橋コレクション』 1962年、春」という展覧会を開催中だった。今からちょうど50年前の1962(昭和36)年にパリ国立近代美術館で、初めて石橋コレクションを紹介する「東京石橋コレクション所蔵-コローからブラックに至るフランス絵画展」が開催された、それを再現してみようという企画である。

日本のコレクターが所蔵するフランスの画家達の作品がパリで展示されるのだから、それらの絵画にとっては「里帰り」になる訳だが、50年前のその絵画展によって、アート・コレクターとしての石橋正二郎の存在は大いに注目を集めたそうだ。
私はいつも、薀蓄を抜きにして絵画を眺めることを楽しむほうだ。どちらかと言えば光が明るくて、色使いが優しく、発想が自由で、眺めているだけでも頭の中が柔らかくなっていくような、そんな絵が好きである。だから、今回並んでいた絵画の中でも、後半部分の作品の方に目が行っていたかな。久しぶりに眺めたピエール・ボナールの明るい風景画や、赤と緑が鮮やかなアンリ・マティスの裸婦像などが印象に強く残った。普段にも増して絵画に明るい光を求めたのは、やはり春が待ち遠しいからか。

絵画展を小一時間楽しみ、外に出てみると、マラソンは銀座方向へと走る列だけになっていた。家内と私は京橋から再びメトロに乗り、表参道へ。ブティック街を通り抜けて根津美術館へと向かう。そこでの展覧会は家内とって今日の一番のお目当て、「虎屋のお雛様」である。
羊羹で有名な和菓子の老舗、「虎屋」。1520年代に京都で創業したというから、殆ど「500年企業」という驚くべき存在である。その虎屋で明治の30年代に、当時の店主が娘の初節句のために集めたり特注したりした雛人形と雛道具の一式が展示されている。ポスターの写真に見る通り、雛壇は実に14段(!)、そこに乗りきらない物も含めて約300点の品々が展示されている。(14段の姿は写真だけで、実際に雛壇に乗せるべき雛道具の一つ一つが、個別に展示されている。)

展示物は江戸期に遡るものから明治時代の作まで様々だが、個々の雛道具はまことに小さなものだ。豆粒ほどの大きさながら、食器や重箱などが極めて精緻に再現されている。なぜここまでのミニチュアをわざわざ作ったのかというと、江戸時代に幕府からたびたび倹約令が出て、雛人形の大きさ(高さ)を制限されたことによるものだという。人形を小さくするなら、道具類もそれに合わせて更に小さく、という訳だが、そういう微細なものを本物と見間違うほど精緻に作ろうとするこだわりが、いかにも日本人のDNAなのだと、改めて思わざるを得ない。遠い祖先の時代から、私たちはこういうことが好きなのである。

京都の風だから、雛人形や道具の飾り方は関東のそれとは異なるところがあり、「あれっ? どっちが左でどっちが右だったっけ?」などと言いながら、家内だけでなく私も結構楽しませてもらうことになった。
雛祭りといえば、いまだ寒い頃ながら、かすかな春の到来を慶ぶ時期である。その3月3日まであと一週間。冬の寒さはまだ続きそうで、一足飛びに春がやって来る訳ではないから、もう少し我慢をしなければならない。今日は、まだ見えぬその春を探すようにして歩く、家内との半日になった。
なお、「虎屋のお雛様」は3月4日になってもあたふたと片付けられてしまう訳ではなく、展覧会は4月8日まで続くようである。



