某重大事件 [読書]
それにしても、日露戦争の頃の日本は現実をよくわきまえ、貧乏国が大国ロシアとどう戦うか、そのことをみな必死になって考えていたのに、それが終わると「戦勝体験」から政府も軍部も国民も途端に夜郎自大になった、という風に語られることが多い。確かに、1905(明治38)年のポーツマス条約の交渉でロシアから賠償金が取れないことが解ると、日比谷焼打事件が起きて戒厳令が敷かれる騒ぎになったし、10年後の1915(大正4)年には、第一次世界大戦の勃発に乗じて火事場泥棒的な「対華二十一箇条要求」を国民政府に突きつけている。いわゆる「満州事変」の発端となる柳条湖事件が起きたのは、それから16年後のことだ。「明治は偉大だが、戦前の昭和は全く別の生き物のようだ」というのは「司馬史観」でもある。
かつての日本史の教科書を改めて紐解いてみると、その「不可解な昭和史」の冒頭に書かれているのが、「満州某重大事件」というこれまた不可解な事件である。1928(昭和3)年6月4日の早朝に起きた、満州軍閥の親玉・張作霖が奉天へ帰還すべく北京から乗った列車が爆破され、張が暗殺されたという、「張作霖爆殺事件」のことだ。
日露戦争で流した将兵の血の代償として満州に様々な権益を持っていた日本は、蒋介石の国民政府による中国統一を望まず、満州軍閥の張作霖を支援してきたが、その張が日本の思惑通りに動かなくなったので、日本陸軍が謀略をめぐらせて暗殺したという。首謀者は関東軍参謀の河本大作大佐であったとされるが、それは終戦まで公表されなかった。
浅田次郎の新作『マンチュリアン・リポート』(講談社)は、この事件を題材にした非常に興味深い作品だ。

「満州某重大事件」という名で呼ばれたように陸軍が事をウヤムヤにしようとする中、事件の真相究明と関係者の厳正な処罰を求める昭和天皇が自ら密使を送るところから話が始まるのだが、そこから先の話の展開をその密使自身に語らせる章と、張作霖の乗った列車を牽引する蒸気機関車を擬人化して語らせる章とを交互に織り交ぜ、マルチ・スクリーンを見ているような気分でストーリーの展開を楽しむことができる。
よく考えられた構成で、事件と同じルートを辿って密使が奉天に近付くにつれ、話が盛り上がっていく。そして、その結末たる最終章も実によく考えられているのだが、勿論ここでは触れないでおく。
更に言えば、馬賊出身の張作霖が、これはこれで英雄として人望を集めた魅力ある人物として描かれているところが、私には新鮮であった。
.jpg)
この事件は、要するに線路に爆薬を仕掛けて走ってくる列車を吹っ飛ばしたのだろうと単純に想像してしまいがちだが、実はそうではない。歴史の教科書にも載っていた写真を思い出すと、爆破された列車の車体は上部が吹き飛ばされたように大きく壊れ、焼け焦げているが、台車はレールに乗っていて脱線していない。だから、地面からの攻撃ではないのだ。以前から明らかになっていることは、
①張作霖を乗せた列車が走ったのは京奉鉄路という、英国の借款により建設された中国側の鉄道で、奉天軍の兵士が要所要所で歩哨に立っていたであろうから、日本軍が彼らの目につかぬように大量の爆薬を線路に仕掛けることは不可能に近かった。
②爆破の現場となった皇姑屯という場所は、京奉鉄路の終点・瀋陽駅のすぐ手前で、日本が権益を持つ満鉄・連長線が京奉鉄路をオーバークロスする箇所だった。(満鉄の沿線なら関東軍の守備範囲で立ち入りができる。) そして、上を走る満鉄に仕掛けられた爆薬によって鉄橋が崩れ落ち、下を通る車輌が押し潰された。(その直後に満鉄の列車が現場を通過せぬよう、満鉄側にも予め何らかの連絡が行っていたはずである。)
③蒋介石の国民政府軍との戦いに敗れて奉天への撤退を決めた張作霖は、これは敗走ではなく故郷奉天への凱旋なのだというポーズを取るために、列車を時速10キロほどの低速で走らせていた。(だから満鉄のオーバークロスの鉄橋で、張作霖が乗っている車輌をピンポイントで狙うことができた。)
④張作霖を乗せた列車は、25年前にあの西太后が祖先の墓参りをするために乗った「お召し列車」として製造された、超豪華列車だった。(但し、警戒心の強い張作霖はその前後に囮(おとり)列車を走らせていた。)
⑤現場には、「これが犯人でござい。」とでも言わんばかりに、阿片中毒の中国人二人の死体が転がっていた。
などで、吟味してみるとなかなか奥深いものがある。勿論、浅田次郎の小説もこうしたポイントを踏まえてストーリーを展開させている。
.jpg)
事件発生直後から「陸軍の陰謀」の匂いがしたが、自らも陸軍大将であった当時の首相・田中義一は腰が重い。元老・西園寺公望に再三促されて、事件発生から半年以上も経ったクリスマス・イブの日に宮中に参上し、「十分に調査し、もし陸軍の手がのびているようであれば厳罰に処する」旨を天皇に報告して了承を得たが、そこから先はいよいよ陸軍の抵抗を受ける。
結局、翌年(昭和4年)の5月になってから再び天皇の下へ行き、「調査の結果、本件に陸軍の関与は一切ない。但し、日本が手を組んでいた張作霖を警備するという点では結果的に関東軍に責任があるが、それは軽微な処分で済ませたい。」という報告をして天皇の逆鱗に触れた。
「田中は再び私の処にやって来て、この問題はうやむやの中に葬りたいと云う事であった。それでは前言と甚だ相違した事になるから、私は田中に対し、それでは前と話が違うではないか、辞表を出してはどうかと強い語気で云った。こんな云い方をしたのは、私の若気の至りであると今は考えている。」
(『昭和天皇独白録』 寺崎英成 編、文藝春秋)
首相が「お前はもう辞めたらどうだ?」などということを天皇から直々に言われてしまったのは、後にも先にもこの時だけだろう。天皇が辞任を迫ったのは実際には翌6月の事件に関する最終処分案の報告の時であったようだが、天皇から再三の叱責を受けた田中は7月2日に内閣総辞職を決意。そして失意のまま9月に生涯を閉じた。天皇はその報せに衝撃を受け、
「この事件あって以来、私は内閣の上奏する所のものはたとえ自分が反対の意見を持っていても裁可を与える事に決心した」
(前掲書)
という経緯はよく知られているところである。結果的に、その後の昭和史を方向付ける「沈黙の天皇」を生むことになる事件であったとも言える。
なお、首謀者とされる河本大作の『私が張作霖を殺した』と題する手記が、昭和29年になって文藝春秋から発表されている。戦前に本人が記録を残す目的で義弟に筆記させたものだそうだが、これはネット上でも読むことができる。大変に興味深い内容である。

(河本大作 1883~1955)
張作霖爆殺事件の処理を巡って内閣は倒れたが、河本は軍法会議にかけられることもなく、予備役編入という軽い処分になり、その後は満鉄の理事に就任。更には国策会社の山西産業の社長になった。日中戦争の終了後も山西省に留まり、国民党軍に協力したが、1949年に共産党軍の捕虜になり、太原の収容所で1955年に病死している。享年72歳。
激動の東アジアを舞台にしたその生涯は、「不可解な昭和」の一つの象徴なのだろうか。
山の絵本 [読書]
本来ならば日曜日の今日は台風一過の秋空を期待したいところだが、西から新たに気圧の谷がやってくるため、月曜日までは雨模様の天気が続くという。こればかりはどうなるものでもないので、雨の日曜日は本を読んで過ごすことにする。
詩人・尾崎喜八(1892~1974)は、よく晴れた明るい景色の中にも初秋の気配が漂い始めた蓼科の山を歩いている。
「一天晴れて日は暖かい。物みな明潔な山地田園の八月の末。胡麻がみのり、玉蜀黍(とうもろこし)が金に笑みわれ、雁来紅の赤や黄の傍で、懸けつらねた干瓢が白い。この土地で高蜻蛉(たかとんぼ)と呼ぶ薄羽黄蜻蛉の群が、道路の上の空間の或る高さで往ったり来たりしている。 (中略) ふりむけば少しのけぞった蓼科山。だが私はもう少し前から、御牧ガ原の空に舞っている一羽の鳥を、鷹ではないかしらと気をつけている。
シャンパンのように澄んで爽やかな、酔わせる日光。ガブリエル・フォーレの、フランシス・ジャムの秋。健康な胃の腑が火串であぶった鶫(つぐみ)の味を夢みる秋……」
(「たてしなの歌」より)
歳月を経てもなお色褪せることのない、瑞々しい表現。これは昭和9年に書かれたものだ。国全体が次第に戦争へと駆り立てられていった時代に、何と自由でおおらかな発想だろう。尾崎喜八のこうした散文を集めた『山の絵本』(岩波文庫)は、先週から私をその虜にしている。

尾崎喜八は若くしてロマン・ロランや白樺派の影響を受けて文学に傾倒し、高村光太郎や武者小路実篤らと交友を重ねた。ロマン・ロランやヘルマン・ヘッセの作品を原文で読みたいがために、フランス語はフランス人に習い、ドイツ語は独学したという。そのロランとは書簡も往復している。そうした詩や随筆の訳業を続けながら、自らも自然と人間をテーマにした詩文を発表するようになった。自然が好きで、山歩きが好きで、クラシック音楽への造詣が深く、天文学や気象観測にも興味を持ち・・・とくれば、この人はやはり本質的に詩人だったのである。
確かに、彼の作品には音楽の話がよく出てくる。ガブリエル・フォーレは1924年に生涯を閉じる直前まで数多くの作品を手掛けていたから、尾崎喜八にとってはある意味で同時代の作曲家なのだが、それにして、もこの時代に晩夏の蓼科の情景をフォーレの音楽に例える感性には驚くばかりだ。また、冬の朝、小淵沢から小海線の列車に揺られている時のことは、こんなふうに表現している。
「甲斐小泉、甲斐大泉。ドビュッシイの管弦組曲を想わせるような、雪に埋もれた高原の小停車場。純潔な山岳の結晶群と、清澄な一月の天へ登極する午前の太陽、終点まで五十分のあいだ、私たちはこの支線の美を温床(フレーム)列車の窓硝子の氷の孔から味わえるだけ味わって、そして酔った。」
(「御所平と信州峠」より)
山歩きを好んだ尾崎喜八。だが、彼はいわゆる「登山家」ではない。『山の絵本』に収録された散文も、そこで取り上げているのは、一般的にも知られた山域である。中には、山に登るのではなく、麓の道を歩いて冬の山々を眺める、今で言えばトレッキングのような旅もしている。そして、そんな山歩きを通じて、その土地に暮らす人々を見つめ、時には地元の子供達と無心になって遊ぶ、その目が優しい。
「さようなら、国界の小さい子たち!この小父さんはまた来るだろう。甲斐や信濃で山々を吹く風が、とおく都へ伝わって来る時、小父さんは杖をとり上げて君たちの方へさまよい来ずにはいられまい。だが多分今度の時には、君たちの家のうしろを高原列車というのが走り、都会の卑小と軽薄とが、この素朴で大らかな野山一帯に、百貨店の包紙といっしょに撒き散らされることになるだろう。
それならば、これが『さらば』だ。思い出の中でのみ滅びないものよ、さらば!」
(同上)
敢えて注釈を加えれば、昭和10年1月初めの時点では、現在のJR小海線の小淵沢方は清里までしか通じていなかった。野辺山という日本の鉄道では最も標高の高い所に線路が敷かれ、佐久海ノ口で小海線の全線がつながったのは、この年の暮のことなのである。
昭和10年5月、尾崎喜八は友人と大菩薩連嶺の大蔵高丸・大谷ヶ丸に向かった。夜汽車で笹子トンネルを越え、初鹿野(現在の甲斐大和)駅を降りたのが午前3時。そこから(当時は舗装などしていないはずの)道路を5キロ近く歩き、更に大蔵沢という沢を遡行して大蔵高丸を目指したのである。
.jpg)
このあたりは私も好きな山域なのだが、今でも結構山深いところだ。何といっても、笹子峠の両側に立ちはだかるのは、山梨県を東西に二分する山々である。その尾根を貫く中央本線の笹子トンネルが開通したのは明治35年。その時点では日本最長のトンネルだったのだ。その笹子の山の険しさを尾崎喜八はいとも平明に、しかし的確に描写している。私などは、ただ脱帽する他はない。
「笹子をこえて人は甲州国中(くになか)の平野へすべり込む。錯覚をおこしそうな眼がぼんやり見ていたスイッチバック、三方から倒れかかって来そうだった山々の壁、あの郡内初狩の名をまだすっかりは忘れてしまわぬ内に。
振りかえって見上げると、今抜けて来た山のまっくろな影絵の上に際立ってあざやかな一つの光。甲州路の旅の晴天をいつも予言する星の光だ。心がまだ見ぬ今日一日のために歌い出す。しかし夜は明けない。世界は陰沈と眠っている。一行七人、われわれもまた黙々として進む。」
(「大蔵高丸・大谷ヶ丸」より)
今は大蔵高丸から尾根続きの湯ノ沢峠までマイカーで上がれる時代になり、夜汽車はなくなったが、昔の人は文句も言わずに駅から歩いたのである。それも、大蔵高丸から稜線上を大谷ヶ丸へ南下し、更に滝子山を越えてその日のうちに鉄道で帰京する計画だったというから驚いてしまう。その日は天候に恵まれ、尾崎喜八は尾根の上から山々の眺めを存分に楽しんだようだ。
決して平坦な人生ではなかった。幼くして両親は離縁し、里子に出された。高校を卒業後、高村光太郎に出会い文学や詩作に惹かれていくが、父はその道を好まず、一度は廃嫡を受ける。同時に、初恋の相手を病気で失っている。関東大震災と太平洋戦争で共に被災し、住居は転々とした。父の生家のある東京・中央区での生活にはなじめず、自然の残る世田谷の高井戸での暮らしを好んだ。終戦の翌年からは長野県の富士見で11年を過ごし、その後は世田谷の上野毛、そして北鎌倉などの緑の中で、持病の胃潰瘍を抱えながら静かに暮らした。
私が大学生の頃、『冬の雅歌』という尾崎喜八の詩文集を読んだことがある。その中には前述した富士見での暮らしを描いた文章も収録されていた。世の中はまだ混沌としていた昭和20年代。尾崎喜八は富士見から汽車で上京し、子供や孫の顔を見た後、丸善で本を買い求めて富士見に戻る。そして庭の落葉を掃き集めて焚火をしながら八ヶ岳を眺め、家族と過ごした束の間の時を静かに思い出している・・・。確かそんな内容だった。淡々とした文章ながら、私は静かな感動を覚えたものだった。
尾崎喜八が富士見に移り住んだのは昭和21年。彼が54歳の時である。奇しくも同じ歳になった私は、文庫本を通じて再び尾崎喜八の世界に出会った。そして、学生時代以来の山歩きを楽しんでいる。
火曜日からは晴天が戻るという。富士山は冠雪しているだろうか。山々の紅葉は進んだだろうか。晴れる毎に遥かな山々の眺めが楽しみな季節である。
自由(まま)投票 [読書]
この暑さの中、民主党は現首相と「陰の実力者」が二週間後の党代表選挙で正面から対決することになった。この時期に政争を国政に優先させる理由が全くわからないが、「挙党態勢」や「トロイカ指導」という意味不明の言葉で煙にまかれるよりは、この際シロクロはっきりさせた方がいいという声が多いのも確かなようだ。
伝えられるところ、今回は二人の候補者に対する「民意」にかなり明確な差が出ている。そんな中で、特に小選挙区から選ばれた衆議院議員たちが、自らが属するグループの論理を優先させるのか、「民意」を強く意識するのか、これは事後的に分析してみると面白そうである。(その「民意」にも地域差はあるのだろうが。)
議会で採決を行う場合、米国では個々の議員達に対していわゆる「党議拘束」というものがないそうだ。だから、オバマ政権が議会に提出した医療制度改革法案に対して、民主党議員であっても個人の判断で反対なら反対票を投じる。今やインターネットの時代だから、各議員に対しては選挙区の有権者から容赦なくメールが届き、各議員がどの法案にどんな票を投じたかはネットで簡単にわかる。議員はそうした「有権者の目」を意識しながら判断を下し、その結果反対票を投じても、日本における「造反議員」のような扱いを受けることはないという。
それが米国型の議会制民主主義であるとすれば、何につけてもまずは党内の派閥(民主党の場合は「グループ」)による拘束がある、というのは非常に日本的なそれである。現代の国会議員にとってすら、政策に関する主義主張の自由は組織の論理に劣後するものなのだ。そういう社会のあり方というのは、どこにルーツがあるのだろう。
建武元(1338)年8月、京都鴨川の二条河原に、誰が書いたか、後醍醐帝による「御新政」以後の混沌とした世情を風刺するリズムのいい文書が掲げられた。世に名高い「二条河原の落書」である。
此比(このころ)都ニハヤル物 夜討強盗謀綸旨(にせりんじ)
召人(めしうど)早馬虚騒動(そらさわぎ) 生頸(なまくび)還俗(げんぞく)自由(まま)出家
俄大名(にわかだいみょう)迷者 安堵恩賞虚軍(そらいくさ)
(中略)
譜第非成ノ差別ナク 自由狼藉ノ世界也
(以下省略)

この中で、「自由出家」や「自由狼藉」という言葉が目に留まる。前者は、出家したと称して大番役(京都の宮廷の警護)を逃れようとする御家人が後を絶たないため、鎌倉時代には幕府の許可を得ない出家が禁じられていた、それが守られていないという意味だそうだ。また、治安を守る者がいないのをいいことに、やりたい放題の狼藉をすることが後者である。いずれも「勝手気まま」、「やりたい放題」、「何でもあり」というのがここでいう「自由」の意味であり、従って「けしからん」というニュアンスを込めた言葉なのだという。
この国の歴史の中で、既存の社会の秩序とは無関係に、或いは意図的に秩序からはみ出して生きる新種の人々が登場し、それが社会を変える可能性を持っていた時代が三つあった。その最初の時代である南北朝時代を、そうした新種の人々に光を当てながら掘り下げたのが、『自由にしてケシカラン人々の世紀 - 選書日本中世史2』 (東島 誠 著、講談社選書メチエ)である。(因みに、残る二つの時代とは、著者によれば戦国時代と幕末維新の時代である。)

本書でいう「自由にしてケシカラン人々」とは、大衆芸能として新たに登場した猿楽や田楽を見せて諸国を旅する芸能民であったり、或いは各地を歩いて勧進聖(かんじんひじり)などと呼ばれた遊行僧であったり、年貢の運送を担う者であったり、いずれにしても一箇所に定住しない人々のことだ。既存の社会秩序から外れて生きていることを誇示するために、彼らはみな奇天烈な風体をしていたという。それが、貴賎を問わずこの時代の人々の注目を集めたようだ。
「四条橋復興の勧進興行(チャリティーコンサート)の場面で見物席が倒壊し、死者百余人を出す大惨事となった。その見物客の中に、天台座主(ざす)梶井宮尊胤法親王と将軍足利尊氏が含まれていたことが(『師守記』という当時の日記に)記されている。さらに『太平記』によれば、関白二条良基もその場にいたということだ。」
(前掲書)
なかなかユーモラスな光景を想像してしまうが、こうした興行一座は移動しながら各地の権力者や名士とコネクションを持ち、諸国の事情に明るく、中には土木や建設の技術を持つ人々もあったという。15世紀になると、飢饉のたびに都に難民が押し寄せる中、興行のある場所で粥の炊き出しを行い、有力者をスポンサーとする(橋の修復などの)建設工事を請け負い、それが一時的にせよ難民に仕事を与えることで都市の混乱を防ぐ役目を担っていたとも。そして鎌倉時代の中期以降、次第に勃興していく流通経済や貨幣経済は、こうした非定住型の人々の存在を抜きには語れないようである。
この他にも、荘園体制を下から掘り崩していくような、支配側からは「悪党」と呼ばれた新興勢力や、海賊行為を働いた連中もあった。それらの総体が、「自由にしてケシカラン人々」なのだろう。確かにそれは、既存の社会を大きく変えていく可能性を持っていた。

だが、新たな混乱は新たな秩序もまた求めようとする。本書が興味深いのは、一般にはそのあたりから社会の崩壊が始まったと思われている応仁・文明の乱(1467~77)以降の時代が、混沌としつつも近世的な秩序を作りつつあり、社会の更なる解放という方向ではなく、むしろ閉塞に向かい始める時代であったと指摘していることだ。
今から思うと、私達が学生の頃はまだマルクス歴史学の影響が強く残っていて、室町時代後期の「惣村の成立」に入ると、先生の話には力がこもっていたものだった。正長の土一揆(1428年)、山城国一揆(1485年)などは、まるで人民による「臨時革命政府の樹立」であるかのような話ぶりだった。
だが、著者によると、惣村が守護勢力から一定の「自治権」を獲得した代わりに、公権力化した惣村の中では新しいヒエラルキーが作られ、統治がむしろ厳格なものになっていったという。
「中世後期に高揚する惣村自治とは、より大きな『オオヤケ』に抗する小さな『オオヤケ』を作り出しただけであって、いったんより大きな『オオヤケ』に呑み込まれれば、それは支配にとってきわめて親和性の高いシステムとなる。それゆえそれは、ヴェーバー風に言えば、ライトゥルギー的な支配の末端機構へと、容易に転化していったのである。」
(前掲書)
一方、15世紀の飢饉の時には難民が容易に流れ込んだ京都のような都市はどうか。戦国時代に入り、都市民が「町」単位の自治を獲得するようになると、それとの引き換えで他所者に関する情報提供や犯罪者の捜査などに「町衆」が協力することになり、異分子にとっては生きにくい場所となっていったと述べられている。そして、応仁・文明の乱であれほど混乱・荒廃したイメージのある時代に、国全体の生産力は上がり、経済は拡大に向かったと見られているのである。
間もなく戦国時代に入ろうとする日本。群雄割拠と下克上の世を迎えていくのだが、中世に「自由にしてケシカラン人々」が跋扈した社会は、惣村にしても都市にしても次第に統制色が強くなり、そういう人々が社会の異分子として「自由に」生きていくことが難しくなっていく。
そして迎えた戦国時代は、既に形作られつつあったそのような社会の構造を破壊するものではなく、それを受け継ぎながら近世へと「脱皮」していくための一つの過程であった、というのが本書の見方である。更に秀吉の時代になると、中世には勧進聖の仕事だった架橋も被災民の救済も、そして京都の方広寺に大仏殿を建てるような宗教的行為でさえも公権力の役目となる。「自由でケシカラン人々」によるネットワークが世の中の隙間を埋めた時代は過去のものになっていった。

さて、今の日本はどうだろう。「戦後の民主化」を経て、今の我々は「ケシカラン」というニュアンスを込めた言葉遣いではない、近代以降の概念としての「自由」を前提とした社会体制の中に生きている。だが、中世後期の惣村や自治都市が、一定の範囲内での自治権と引き換えに統制色のある閉塞した社会を形作っていったのとある意味同じようにして、国民は「自己責任を問われずに済む気楽さ」と引き換えに「自分でモノを考えて行動する自由」を権力者に渡してしまう、実に閉塞した社会を続けてきてしまったのではないだろうか。
「脱官僚支配」や「政治主導」を叫ぶのであれば、それを実現するものは何よりも政治をきっちりとモニターする国民の目である。それは、「誰かにお任せ」ではなく、「場の空気に従うこと」でもなく、「自分でモノを考えること」なのである。
自民党政治へのアンチテーゼとしてそれを唱え続けてきたのであれば、自分達のリーダーを選ぶのに、個々人は何をどう考えてどんな結論を出すのか。国会議員、一般党員、サポーターを含めた民主党の人々は、自らの行動が自らに跳ね返って来ることを心すべきであろう。
いつか来る別れ [読書]
百歳を超える長寿といえば、大変おめでたいことである。私の母方の祖母もその一人で、数年前に百歳を迎えた時には皆でお祝いをしたものだ。私を含めて孫が19人、曾孫は30人を超え、そこまでは一同に集まれないから孫と曾孫は寄せ書きになった。
その祖母は今のところ公的な介護を受けることもなく、湘南の海沿いの温暖な地で静かに暮らしている。別棟に叔父の一家がいて毎日の生活は一緒だが、それに加えて母の兄弟が入れ替り立ち替り祖母の様子を見に行っている。母の世代は兄弟が多いからそれが可能なのだが、母も叔父叔母たちもさすがに歳をとってきた。東京から電車に乗って、或いはクルマで東名高速を走って、祖母の様子を見にいくことがいつまで続けられるだろうか。
いずれにしても、私の親類はそんな風だし、家内の家系も祖父母の代は子供や孫に囲まれて天寿を全うした人たちだ。だから、百歳を超えたことになっているお年寄りについて、家族の誰に聞いても所在を知らない、「20年前に会ったきり、行方がわからない」などという報道を目にすると、一体どんな事情があってそういうことになるのか、私にはちょっと想像がつかないところがある。
新聞の解説によれば、そうした長期間の所在不明にはいくつかのパターンがあるという。
認知症による徘徊で「ふらっと家を出たきり帰ってこない」というのが一つ。これは今後も増え続ける見込みだそうだ。二つ目は、配偶者に先立たれた、生涯独身、「子供の世話にはなりたくない」等の理由で独居する老人がやがて生死不明になるパターン。これも益々増えていくのだろう。そして三つ目は、同居しているはずの家族共々行方不明になってしまうケースだという。
そうしたお年寄りが日本のどこかで命の終焉を迎えた時、身元不明のままで死亡届も出されないということになるのだろうか。今は取りあえず百歳以上のお年寄りが調査の対象になっているが、それ以前の年齢でも同じようなケースはあるはずだ。とすれば、この国で孤独な死を迎える人は相当な数になるのではないか。
「生存確認」が充分できていないことについて、「自治体のお役所仕事」を批判するのは簡単だ。年金や手当の不正受給があるのではないか、家族は何をしていたのかという声も多い。だが、何よりも認識しなければならないのは、我々が既に直面している高齢化社会とはこういうものであり、それは今後数十年にわたって益々深刻なものになっていく、ということだろう。
そんなニュースが続いた今週、一冊の文庫本を手にした。年老いた作家が、自分よりも先立ってしまった妻を思って書き残した手記である。
まだ学生時代、名古屋の図書館で「間違って、天から妖精が落ちて来た感じ」の彼女と出会った時のこと、どんな夫婦でも経験することになる新婚時代のドタバタや涙と笑い、やがて学者との二束の草鞋を捨てて作家生活に専念することになった本人を明るく支える妻。
『小説日本銀行』、『男子の本懐』、『落日燃ゆ』、『粗にして野だが卑ではない』・・・。その作品群と本人の個性から、「硬骨漢」という言葉がこれほど似合う人もなかったこの作家が、妻のことになると心の底からの愛情を臆面もなくさらけ出している。硬派な分だけ、その不器用なまでの一途さが微笑ましくもある。何をするわけでもないが、そばにいて一緒に時を過ごすだけで幸福感に満たされる、清々しい空気のような、そして明るい太陽のような存在。この作家にとって、妻はまさに最良にして最愛のパートナーであった。老後が長く続いても、きっといつまでも仲睦まじく過ごしていったことだろう。
その最愛の妻が、ある時から体調を崩した。後になってみれば、思い当たるふしがあったのだが、もう遅かった。彼女は一日かけた検査に行っているが、恐らくは肝臓癌を宣告されることを、作家は覚悟しなければならない。
心の準備が出来ぬまま、妻の帰りを待つ作家。これから彼女が答えることに、どう応じたらよいのか。しかしそこへ、唄声と共に彼女は帰ってきた。
「ガン、ガン、ガンちゃん ガンたらららら・・・」
癌が呆れるような明るい唄声であった。
おかげで、私は何ひとつ問う必要もなく、
『おまえは・・・』
苦笑いして、重い空気は吹き飛ばされたが、私は言葉が出なかった。
かわりに両腕をひろげ、その中へ飛び込んできた容子を抱きしめた。
『大丈夫だ、大丈夫。おれがついている。』
何が大丈夫か、わからぬままに『大丈夫』を連発し、腕の中の容子の背を叩いた。
こうして、容子の、死へ向けての日々が始まった。」
(『そうか、もう君はいないのか』 城山三郎 著、新潮文庫)

涙が出そうになるから、ここから先は引用をしないでおこう。これは深く胸に響く手記である。そして、巻末に添えられた城山三郎の次女の文章 『父が遺してくれたもの』 を読み、あの硬骨漢・城山三郎が何と素晴らしい家庭を持っていたか、そのことにも大きな感銘を受けた。
最愛の妻に先立たれ、心の中に大きな穴が開いたようになって、
「そうか、もう君はいないのか」
という呟きを繰り返していた城山三郎をその後7年にわたって支え続けたのは、この家族なのである。
家内と私と、いつかはどちらかが残される。残された方は、自分の力でその孤独と折り合っていくしかないのだが、そのことで子供達に迷惑はかけられない。そう思っている人は多いはずだ。しかし、だからといって先に挙げたような独居のパターンになってしまうと、今度はいつか社会に迷惑をかけることになる。
上手に老いて、上手に生涯を閉じていきたいものだが、果たしてそれはどこまで自分でコントロールできるものだろうか。
お盆が近い。この一年に亡くなられた方々のことを思い出しながら、老いていくことの意味を考えてみる季節である。
大国の論理・小国の意地 (3) [読書]
今の私たちは1970年代以降の歴史を知っているから、ドミノ理論に対しても、現実世界はそんなに単純なものではないよ、と言うことができる。だが、戦後のヨーロッパに「鉄のカーテン」が敷かれ、中華人民共和国が誕生し、朝鮮半島が南北に分かれ、そして60年代に入ると米国の喉元のキューバで共産革命が成立し・・・というような情勢下では、ドミノ理論はかなりのリアリティーをもって受け止められていたのだろう。
1964年末から65年の初頭、北ベトナム軍の攻勢と南ベトナム軍の無能、南ベトナム政府の腐敗、そして南ベトナム解放民族戦線が各地で繰り広げるテロ闘争によって、南ベトナムという国は崩壊の一歩手前にあった。このままではドミノ理論の予言する通りになってしまう。米国はそこで、北爆と大規模な地上部隊の投入を決意した。だが、
ベトナム戦争は「歴史上最も複雑な戦争」といわれ、様々な要因がアメリカ軍の行動を制約した。南ベトナム政府と軍の腐敗と無能、北ベトナム政府と軍の強靭な意志と組織、地域の奪取を目的としない不慣れなゲリラ戦、熱帯性ジャングルと山岳地帯という戦場の地形と気候、カンボジア・ラオス・北ベトナムという聖域の存在、ソ連と中国による介入の可能性、迅速かつ安価で犠牲の少ない軍事的勝利を求める国内世論などの制約を一挙に解決することは、アメリカ軍にとって実際上不可能であった。
(『戦略の本質』 (野中郁次郎 他5名共著、日経ビジネス人文庫) 第7章 ベトナム戦争 より)
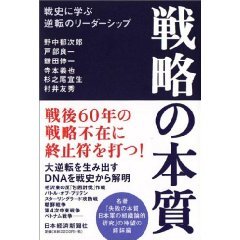
米国が南北ベトナムの戦争に直接介入することにより、無能で崩壊寸前の南ベトナム政府・軍の代わりに米軍が前面に出て、北ベトナム軍や南ベトナム解放民族戦線のゲリラと戦うことになってしまった。米軍は不慣れな地で不慣れな対ゲリラ戦を強いられ、消耗し、その一方で世界からは「アメリカの戦争」と受け止められる。そして、戦地の惨状と、そこまでして米国が支える南ベトナムの腐敗と無能ぶりがメディアによって配信されるたびに、「アメリカの戦争」の正当性が揺らいでいく。
アメリカは自分が常に正義であると考えており、「正義は必ず勝つ」と信じている。したがって、戦場における不成功は、戦争の動機と性格そのものに対する疑念を生み出し、アメリカ国民の戦意を根底から破壊する。このようなアメリカにとって、ベトナム戦争はきわめてやりにくい戦争であった。
(前掲書)
ベトナム戦争によって、米軍には約30万人の負傷者と約58,000人の戦死者が出た。戦場での凄惨な体験から精神を病んでしまった人も多い。これほどの代償を払ったにもかかわらず、北ベトナムによる全土制圧で南ベトナムは社会主義化されたのだから、政治的にも軍事的にも米国の完全な失敗である。他方、その後の世界がドミノ理論の通りにはならなかったことも事実なのである。
前掲書には、こんなくだりがある。
ベトナム戦争を指導したアメリカの中心人物であるマクナマラ国防長官は、ベトナム戦争の教訓として次の点を指摘している。
①共産主義の脅威を過大評価した。
②南ベトナム政府の無能と腐敗を理解していなかった。
③北ベトナムのナショナリズムに基づく信念を過小評価した。
④東南アジアの歴史、文化、政治に対して無知であった。
⑤強い政治的動機を持った人間に対しては軍事技術に限界があることを知らなかった。
⑥大規模な軍事介入を開始する前に、議会や国民の間で十分な討議や論争をしなかった。
⑦複雑な戦争を国民に十分に説明せず、国民を団結させることができなかった。
⑧すべての国家をアメリカの好みにしたがって作り上げる権利をアメリカは持っていないことを認識していなかった。
⑨国際社会が支持する多国籍軍と合同で軍事行動をするという原則を守らなかった。
⑩国際社会には解決できない問題があることを認めなかった。
⑪行政府のなかにベトナム戦争を分析し議論するトップクラスの文官・武官による組織がなかった。
マクナマラ国防長官は次のようにも述べている。
「われわれは正しいことをしようと努めたのですが、そして正しいことをしていると信じていたのですが、われわれが間違っていたことは歴史が証明している。」
上記の①から⑪までについて、ちょっと地名を入れ替えてみるだけで、21世紀になってから行われた「ブッシュの戦争」や、その根底にある米国のネオコン(新保守主義)的な思想の持つ問題点と、何とぴったり重なり合うことだろう。或いは、地名を幾つかの金融用語に置き換えてみるだけで、サブプライム・ローンの焦げ付きに端を発し「リーマン・ショック」を引き起こした米国の金融資本主義の宿痾のようなものまでも、正確に言い当てているかのようだ。
要は、ベトナム戦争以降の米国において、マクナマラの反省は殆ど何も活かされてこなかったのだ。
最後に、今回読む機会を得た『我々はなぜ戦争をしたのか - 米国・ベトナム 敵との対話』 (東大作 著、平凡社ライブラリー)から、以下の部分を引用して、今回の結びとすることにしよう。
チャン・クアン・コ(当時、北ベトナム外務省対米政策局長)
私は1967年の夏に行われたマックスウェル・テーラー元アメリカ統合参謀本部議長の旅を思い出します。彼はアメリカの同盟国である東南アジア六か国を訪問しました。その結果明らかになったことは、東南アジアの国々で、アメリカの信ずる「ドミノ理論」を正しいと考えている国など一つもなかったという事実です。ドミノの一つであるはずのシンガポールでさえ、アメリカの派兵要請に応じませんでした。アメリカはまるで、共産主義拡大の被害者を想像の世界で作り出そうとしているみたいでした。被害者であるはずの当人は、アメリカが作り出した「ドミノ理論」に関心などなかったのです。
この点は、本来、外交的に洗練されているはずのアメリカやその他の大国にとって、大きな教訓であるはずです。つまり、検証するのを怠ったまま、国際政治の理論など信用しないで欲しいということです。他の言い方をすれば、「自信過剰になるな。傲慢になるな。あなたの信念を他国にも話し、正しいかどうかを検証せよ」ということです。
大国の論理・小国の意地 (2) [読書]
ベトナム戦争の和平を定めた1973年1月のパリ協定から24年の歳月を経て実現した、米国とベトナムの「ハノイ対話」。四日間続けられた熱い討議の口火を切ったのは、やはりロバート・マクナマラだった。
1961年から8年間にわたって彼が米国防長官を務めたために、この戦争は「マクナマラの戦争」とも呼ばれた。1995年に世に出した『回顧録 - ベトナムの悲劇と教訓』において、マクナマラはベトナム戦争が米国の犯した過ちだったと率直に認めたが、それには賛同も寄せられたものの、右からも左からも数々の批判を受けていた。それだけに、彼をはじめとする米国側には、なぜ戦争を回避できなかったのか、なぜ早期に収拾できなかったのか、その「両国が共に取り逃がした機会」について議論し、結論を米国だけの過ちとはさせたくないとの意図が始めからあったのだろう。

対するベトナム側は社会主義国である。「人民の政府」を標榜するこうした国は常に無謬性にこだわり、自らの過ちを認めようとしないものだ。それだけに、この「ハノイ対話」は初日早々から白熱した議論となった。(以下、青字部分は本書からの引用。)
チャン・クアン・コ(当時、北ベトナム外務省対外政策局長)
アメリカは四つの基本的な問題についてベトナムを誤解していました。それがアメリカの誤った情勢判断につながったのです。その四つとは、
①ベトナム統一こそが、我々ベトナム人の最終目的であったことを理解できなかった。
②南ベトナム解放民族戦線の目標が、国家の解放と独立であったことを理解しなかった。
③ベトナムと他の諸国の伝統的な関係を理解できなかった。 (中略) ベトナム革命は確かに共産主義革命であったが、それは周辺の国々まで共産化しようとするものではなかった。
④ベトナムとソ連および中国との関係を理解できなかった。我々は相互依存関係にあったが、決して、中国やソ連から指示・命令されるものではなかった。 (中略)
私の考えでは、ベトナムは一つ大きな過ちを犯しました。それは1945年の8月まで、アメリカこそが植民地主義に反対する唯一の大国であると考えていたことです。
ニコラス・カッツェンバーク(当時、米国務次官)
ベトナムの皆さんに反論したい。 (中略) アメリカが第二次大戦以後、一貫して植民地主義に反対してきたのは誰の目にも明らかではないですか。
グエン・ディン・ウォック(当時、北ベトナム防空軍将校)
(中略) 1963年から64年にかけて、南ベトナムでは14回もクーデターが起こりました。その度にあなた方は、ゴ・ディン・ジエム政権を必死に救ったのです。なぜあなた方は、腐りきったジエム政権を支持し続けたのですか。アメリカの言いなりになる傀儡政権が欲しかったからじゃないですか。これは植民地主義ではないのですか。
ダオ・フイ・ゴク(当時、北ベトナム外務省対米政策局長)
我々の戦争の目的は、独立と自由でした。自由、独立、国家の統一、それがベトナム国民の共通の願いでした。だからこそ、我々はこの戦いを受けて立たなければならないと考えたのです。しかし、あなた方アメリカは、そうしたベトナム人の気持ちを理解することができなかった。我々を国家としてでなく、冷戦というゲームの中の駒として見ていたのです。
ロバート・ブリガム(米、バッサー大学準教授)
(中略) アメリカは確かにアジアについて無知だったかもしれません。しかし無知の責任の一端はベトナム側にもあるのではないですか。あなた方はアメリカの政策責任者に対して、ベトナムが何を目指しているかということや、平和的解決を望んでいることなどを、全く説明しなかったのではないですか。
グエン・カク・フイン(当時、北ベトナム外務省対米政策局員)
あの状況でどう説明しろというんですか。我々は、アメリカと戦争を始める前に、10年間もジャングルの中でフランスとの独立戦争を続けていたんです。 (中略)
ロバート・マクナマラ(当時、米国防長官)
(中略) 私は、あなた方にもやはり落ち度があったと言いたい。あなた方は当時、今日のように我々に説明すべきだったのです。ソ連や中国の手先となって動くつもりはない、とはっきり言うべきだったのです。
戦争を戦う敵の意思や目的は何なのか。
この最も基本的な情勢判断さえ、双方は全く異なる認識を持っていたことを対話はあからさまに暴露している。
こうした当時の情勢判断に関するやりとりに続き、議論は「戦争回避の道はなぜ消えたのか」、「なぜ全面戦争に突入したのか」、「なぜ秘密和平交渉は失敗したのか」についても切り込んでいく。中でも圧巻は、1965年から68年までの、ベトナム戦争が最もエスカレートしていた時期に米国から働きかけられた、延べ7回にわたる秘密和平交渉に関するくだりである。

チャン・クアン・コ(当時、北ベトナム外務省対外政策局長)
65年から67年にかけて、我々は常に北爆という脅迫を受けながら、和平交渉を持ちかけられていました。こんな状況で交渉に応じることなど絶対にできません。我々に何の迷いもありませんでした。ただ拒否するのみです。
一方でアメリカは、入れ替わり立ち替わり様々な仲介人を送り込んできました。 (中略)
あなた方は、世界中に向かって、交渉によって平和を求めているのはベトナムではなく、アメリカなんだと宣伝したかったのでしょう。あなた方は、北爆という最も非人道的な行為を正当化するために、あらゆる手段を使って「戦争を欲しているのはベトナムなんだ。アメリカは平和を求めている。しかし、ベトナムがそれに応じないから北爆を続けざるを得ないのだ」と世界の人々に印象づけようとしたのです。 (中略)
ロバート・マクナマラ(当時、米国防長官)
冗談じゃない。アメリカの交渉への努力は、決してプロパガンダのためなんかじゃありません。 (中略) 我々はあなた方の国を破壊し、ベトナム人を大量に殺害し、かつアメリカ人にも大きな犠牲を与えたあの戦争を一日でも早く終わらせたいと考えていたのです。だから本気だったか、そうでないかなど議論する気もありません。本気だった、そして失敗した。それが事実です。
ニコラス・カッツェンバーク(当時、米国務次官)
チャン・クアン・コ氏に伺いたいのですが、我々が真剣に和平を模索していると受け止めてもらうためには、一体どうすればよかったのですか。
チャン・クアン・コ
簡単なことです。北爆をやめる。それしかないでしょう。爆弾を際限なく落としておきながら、和平案を信用しろというのは、どだい無理な話です。ましてや、地上軍もどんどん送りこんでいる状況での和平交渉など、信用できるはずがありません。
ロバート・マクナマラ
ベトナムの皆さんに聞きたい。65年の終わりから68年の3月まで、ベトナムの人々、特にハノイに住む人々はものすごい数で犠牲者を出し続けました。 (中略)
一体なぜあなた方は、このような膨大な人命の損失に心を動かされなかったのですか。目の前で国民が死んでいく中、犠牲者を少しでも少なくするために交渉を始めようという気にはならなかったのですか。 (中略)
チャン・クアン・コ
マクナマラさん。あなたは、ベトナムの指導者が、ベトナム人民の犠牲と苦しみを省みなかったとおっしゃりたいんですか。だから我々が、和平交渉に応じなかったとでも言うんですか。 (中略)
いいですか。ベトナム戦争は、ここベトナムの地で行われたという事実を忘れないでもらいたい。ベトナムの国土が荒らされ、ベトナムの人民が死んだのです。戦争の痛みを最も感じたのは、我々だったのです。 (中略) 我々が戦争を続けたい理由が一体どこにありますか。
なぜ、なぜ我々が、あれほど激しい爆撃を受けても、交渉の呼びかけに応じなかったか、あなた分りますか。
それはですね。独立と自由ほど尊いものはないからです。ベトナム人は、奴隷の平和など受け入れないんです。
この最後の点は、四日間の討議が終わってもなお、マクナマラには理解ができなかったようである。だが、マクナマラの発言は、北爆による膨大な犠牲者の発生について、自分達の爆撃によって犠牲者が出ているというよりも、ベトナム人が何か天災にでも遭っているかのような物の言いようで、同じアジア人として、そうすんなりとは聞き流せないものである。
要は、自国の本土で戦争をしたことのない国民には、想像が及ばないことなのだろう。「空爆によって犠牲者が増え続けているのだから、早く和平を交渉すればいいではないか。」 このように、一見合理的な考え方のようでいて、実は極めて独善的な思想が根底にあるところに、米国が世界各地で反感を買う一つの原因があるように、私は思う。
以上、引用したのは本書のごく僅かな部分である。
(to be continued)
大国の論理・小国の意地 (1) [読書]
夏は、書店に戦争物の本が並ぶ季節である。二つの原爆の日、終戦の日、そして始まった占領時代。お盆の時期とも重なって、戦没者を悼み、戦禍を振り返る企画が夏の風物詩のようにやってくる。そんな中で、金曜の夜の会社帰りに一つの文庫本に目がとまった。
1961年から68年まで、米ケネディ政権とジョンソン政権で国防長官を務めたロバート・マクナマラ(1916~2009)をはじめ、当時ベトナム戦争に関わった米国の元閣僚・外交官・軍人ら13人と、同様のポジションで同戦争に関わったベトナム人13人が、1997年6月20日から23日までの4日間ハノイのホテルに集まり、ベトナム戦争を振り返る会合を開いた。
戦争の開始から32年、戦争の終結を定めたパリ協定から24年の歳月を経て実現した「ハノイ対話」。かつての敵同士が一つのテーブルに着いて、第二次大戦後の世界最大の地域紛争となったベトナム戦争を振り返るという画期的なこの会議では、
「お互いの戦争の目的は何だったのか?」、
「この戦争はなぜ回避できなかったのか?」、
「始まってしまったこの戦争はなぜ早期に終結できなかったのか?」、
「話し合う機会をなぜ逸したのか?」
といったことが、冷静に、しかし熱く議論された。そして、そこで明らかになったのは、戦い続けた両国の間での相手に対する驚くべき無知、無理解、誤認であった・・・。
米国側ではプロジェクト「ミスト・オポチュニティ(Missed Opportunities? = 機会を取り逃がしたのか?)」と呼ばれたこの会議の内容は、翌年にNHKスペシャルで98年夏の戦争関連特番として放映され、そのディレクターを務めた東大作氏はその番組を元にした本を2000年3月に岩波書店から上梓した。その復刻版として文庫本になったのが、この夏、書店の店頭に並んでいる『我々はなぜ戦争をしたのか - 米国・ベトナム 敵との対話』 (東大作 著、平凡社ライブラリー)である。
私は当時海外勤務をしていたことから、NHKスペシャルの番組は見ておらず、岩波書店版の本の存在も知らなかったのだが、今回はこの文庫本に出会い、興味深く読むことができた。

ベトナム戦争は、私の年代にとってはかなりの程度、同時代史である。といっても、日本の敗戦を契機に独立の気運を高めたベトナムが、宗主国フランスとの間で繰り広げたインドシナ戦争と、その和平協定である1954年のジュネーブ協定、そしてそのジュネーブ協定に調印しなかった米国が、北緯17度線よりも南に傀儡政権(いわゆる南ベトナム)を作らせたのは、まだ私が生まれる前のことだ。
あくまでも南北統一を目指す北ベトナムは、1959年に南ベトナムの武力解放を決意。翌60年には南ベトナム解放民族戦線(National Liberation Front (NLF)、当初はベトコンと呼ばれた)が結成され、ジュネーブ協定を無視した南ベトナム政権に対するゲリラ活動を本格化させる。広義のベトナム戦争の始まりである。
これに対して1960年に誕生した米ケネディ政権は、共産主義化の動きが東南アジア各国に伝播するというドミノ理論に怯え、南ベトナム軍に派遣する「軍事顧問団」や軍事物資の支援を一気に増強。しかし、独裁と圧政、腐敗で悪名高かった南ベトナムの大統領ゴ・ディン・ジエムは1963年の軍事クーデターで殺害され、その20日後にはケネディ自身もダラスで暗殺される。小学校に上がったばかりの私の記憶に残っているのは、「勤労感謝の日」の朝に行われた日米間のテレビ宇宙中継実験で最初のニュースとして飛び込んできた、”JFK暗殺”を伝える白黒のテレビ画面あたりからである。
そのJFKの後を継いだジョンソン政権時代に、米国とベトナムはいよいよ直接対決への道を進む。1964年夏のトンキン湾事件は、我家では大阪から東京への引越があったりしたので覚えていないが、翌65年2月の北爆開始の時の新聞の大見出しは明確な記憶として残っている。翌月には海兵隊が、そして夏には陸軍部隊が投入され、戦線は急速に拡大することになった。

その頃、小学3年生の私は夏休みで湘南の国府津にある母の実家に長く逗留していたのだが、米軍による大量の地上部隊投入を報じる新聞を広げながら、大叔母が
「これはアメリカがいけないねぇ・・・・」
と呟いた。子供心にも国際社会とは無縁の存在に見えた大叔母までもがベトナム戦争を憂慮するとは、これはよほど大変な問題なのだと私は思ったのと同時に、アジアの小国ベトナムに対して圧倒的な国力を持つ米国が大量の兵力を投入することに、私の周囲の大人たちが総じて批判的であったことを感じたものだった。それはそうだろう。同様の爆撃を受けて日本が敗戦してから、まだ僅か20年ほどの頃なのだ。
大量の兵力を投入しながら、メコン・デルタと密林を舞台にしたゲリラが相手の戦争で、米軍にはなかなか戦果が上がらない。一方で、南ベトナム領内ではNLFによる無差別テロが頻発し、そのNLFに対してはラオス領内を通るホーチミン・ルートを経由して北ベトナムが支援物資を送り続ける。米国内でも北爆の開始と共に始まっていた反戦運動が、1967年頃には大きな社会運動へと広がることになった。
そして、1968年1月の旧正月(テト)の深夜にNLFが南ベトナム軍・米軍に突如として仕掛けたテト攻勢と呼ばれる大攻勢。「戦争はうまく行っている」というそれまでの米軍の公式発表に米国民の疑念が高まると共に、その最中に南ベトナムの警察庁長官が、捕縛したNLFの(まだ裁判にもかけられていない)将校をテレビカメラの前で射殺したことは、世界に大きな衝撃を与えた。そして同年3月に米軍が非武装・無抵抗の村民504名を機関銃で虐殺した、いわゆるソンミ村虐殺事件が明るみに出ると、「この戦争に大義はあるのか?」という声が米国の内外で急速に高まっていく。
マクナマラ国防長官は同年2月に辞任。翌3月にジョンソン大統領は再選を断念。メキシコ五輪が開催されたこの年、私は小学校6年生になっていたが、「テト攻勢」という文字や、ソンミ村虐殺事件を報じる新聞、そしてキング牧師やロバート・ケネディの暗殺を伝えるテレビのニュースなどが記憶に残っている。米国にとっては実に多難な一年だった。
日本で「ベトナムに平和を!市民連合」、いわゆるベ平連の活動が一番盛んだったのはこの時期だろう。「団塊の世代」が大学生だった頃だ。「ベトナム戦争ハンタ~イ!」と叫ぶデモ行進は渋谷の街のあちこちで行われていた。それはやがて大学紛争の時期にも重なっていき、米国からの直輸入のようにしてフォークソングが流行ったものだ。
1969年に入ると、ベトナム戦争は主役が交代する。米軍のベトナムからの「名誉ある撤退」は止むを得ないとする一方で過激化する国内の反戦運動を問題視し、「法と秩序の回復」を訴えて当選したニクソンが大統領に就任。キッシンジャーを国家安全保障担当大統領補佐官に任命して、ベトナムからの段階的な兵力削減を進めつつ、北ベトナム政府との秘密和平交渉を進めさせた。対する北ベトナムでは、長らく独立戦争を率いてきたホー・チ・ミンがこの年の9月に79歳の生涯を閉じている。
1970年代には世界の力関係も変わった。中国とソ連は既に仲違いをしており、その中国を牽制するためにブレジネフのソ連は米国との間でデタント(緊張緩和)を模索。他方、中国も米国との関係修復を図り始めていた。北との秘密和平交渉を優位に進めたい米国は、「ホーチミン・ルート」や「シアヌーク・ルート」を遮断すべく1970年4月にカンボジアへ侵攻。(北ベトナム軍の拠点を叩いて米軍が撤退した後、カンボジアでは泥沼の内戦が続いた。) しかし、ベトナム戦争で撒き散らしたドルの信任が失われ、ニクソンは翌年8月にドルの兌換停止と輸入課徴金の導入を宣言(いわゆる「ニクソン・ショック」)。私が中3の年の、暑い夏のことである。
そのニクソンは翌1972年4月に中国を電撃訪問して北ベトナムを揺さぶる一方、同5月には北爆を再開して強面に出る。この年の12月にハノイを狙って行われた北爆(いわゆる「クリスマス爆撃」)では、反戦を訴える米国のフォーク歌手、ジョーン・バエズが爆撃の最中にハノイのホテルの防空壕でギターを抱え、避難中の各国大使館員らと共に歌い続けたことが大きく報道されていた。
そして1973年1月27日の、ベトナム和平に関するパリ協定の締結。翌々日にニクソンは「ベトナム戦争の終結」を宣言し、3月29日には米軍の撤退が完了した。この年の秋には第四次中東戦争が勃発し、世界は初めての「石油危機」を体験する。ニクソンはウォーターゲート事件によって翌年8月に辞任に追い込まれた。
ドル危機と石油危機後の不況の中で、パリ協定に違反した北ベトナムによる南への侵攻があっても、米国にはそれを阻止するだけの余力がない。米国は動かないと見た北ベトナムは、悲願の南北統一を目指し、1975年3月に南への全面攻撃を開始。僅か一ヶ月で首都サイゴン(現ホーチミン市)に迫り、4月30日にそれは陥落する。

敵軍迫るサイゴンを脱出しようと、南ベトナム政府関係者が米軍・海兵隊のヘリコプターに我も我もとすがる、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』さながらの地獄絵や、赤地に星のマークの旗を立てた北ベトナム軍の戦車が大統領府に突入する映像は、高校を卒業したばかりの私を釘付けにしていた。戦争が終結する瞬間をテレビがここまでリアルタイムに中継したのは、かつてなかったことだ。(そんなことにばかり関心を持っていたから、私はものの見事に浪人していたのである。)
ともあれ、私にとって同時進行形のベトナム戦争とは、こんな風だった。
(to be continued)
成熟フェーズの日本 [読書]
サッカーのW杯大会の一次リーグで日本代表チームが対戦したデンマーク。人口540万人ほどの、ヨーロッパの小国である。
『世界価値観調査2008』という国際的なアンケート調査で、「自分は幸せだ」と思う人の比率が世界一の国、そして健康、GDP、教育、景観などの客観的な指標を比較・集計した『世界幸福ランキング2006』で幸福度世界一となった国は、共にこのデンマークなのだそうである。国民負担率71.7%という、スウェーデンと並び世界で最も税金の重いこの国は、それによって世界最高水準の社会保障、社会福祉を維持し、国民一人当たりGDP(2008年)6.2万ドルはOECD加盟30ヶ国中第4位で、日本の1.6倍にもなる。そして、上述の通り人々の幸福度は主観的にも客観的にも高い。
対する日本は1億2,700万人の人口を擁する世界第二位の経済大国でありながら、国民が豊かさをなかなか実感できない国である。その一方で、「自力で生活できない人を国が助けてあげる必要はない」と答える人の割合が38%と群を抜いて高く(2位は米国で28%、他は先進国も新興国も概ね10%弱)、寄付が世界で最も少ない国でもある。国民の間での所得の格差は比較的小さいが、国全体の平均年収の半分以下の年収しかない「相対的貧困者」が1,900万人(全体の14.9%)も存在することには、余りフォーカスが当たらない。そうした貧困による自殺者の数は、日本が世界一なのである。それなのに、
「新聞も週刊誌の特集も、テレビのコメンテーターも、成長論が見えない、経済成長の戦略が示されていないとばかり騒いでいる。なぜそんなに経済を成長させたいのか。弱者や老人を見捨ててしまえと思っている一方で、やっきになって経済を成長させて何をどうしたいというのか。」
「寄付はしない。弱者を救う必要はない。今、大事なのは経済成長だ。ダム建設は続行しろ。空港をもっと造れ。 日本はこんなことで本当に大丈夫か。」
こんな前書きに引き込まれるようにして読んだのは、『成熟日本への進路 - 「成長論」から「分配論」へ』 (波頭 亮 著、ちくま新書)という新刊本である。
著者の波頭氏は言わずと知れたマッキンゼー出身のコンサルタントで、今までにも切り口の明快な著作を世に出して来た人だ。私とほぼ同年代ということもあり、著作を通じてその思考や分析、論理の組み立てを何かと参考にさせてもらっている人の一人である。
著者は元々、市場主義者の立場で物事を論じてきた人であり、リバタリアン的に規制緩和と自由競争の下で個々人が己の幸福を追求することを説いた著作も出していた。しかし、四~五年前あたりからそれに違和感を持ち始め、
「重視すべきは明確な個性や強い指向性というよりも、基本的な生活の安定である。」
「自分自身のアイデンティティへ向かう内向的な意識のベクトルではなく、他者や社会へ向ける目線や気持ちが、現代の社会においては人々が幸せに生きていく上ではより重要」
というように考え始めるようになった。
では、自らが辿り着いた結論が180度も変わってしまったのはなぜか。そこで著者は思い至る。日本社会の成長フェーズが終わって成熟フェーズに入ってしまったという事実が全ての根源なのだと。
何しろ国の人口が減り続け、高齢者の比率がおそろしく高まるという、世界のどの国も体験したことのない時代に突入しているのである。しかも、その日本は輸出大国と言われるが、GDPの構成比では実は内需の存在が大きい。そこが縮んでいくのだから、今までのような「潜在成長率2~3%」というような経済成長を期待すること自体がもはや無理であり、成熟フェーズに入った以上は公共投資や企業支援で景気を“刺激”しようとしても無駄で、それは老人に無理やり霜降り肉のステーキを食べさせようとするようなものだ、というのが根底にある考え方である。
それでは、成熟フェーズに向けた日本の針路は何か。そこは戦略コンサルタントらしく、波頭氏の提言は明快である。
まず国家ヴィジョンとして、「国民の誰もが、医・食・住を保障される国づくり」を明確に掲げることを説く。一見するとかつての社会主義国家のようだが、そうではなく現在の北欧諸国のように、まずは確かなセーフティーネットを築くために国民同士が社会を支え合うことを指している。
その下での全社戦略として、「産業構造のシフト」が打ち出されている。具体的には、これからのニーズが間違いなく高く、雇用の受け皿にもなる「医療・介護」サービスの拡充であり、そしてエネルギーと食糧の輸入に必要な外貨をしっかりと稼ぐ産業(具体的にはハイテク型環境関連産業)の育成である。
更にその下の個別戦略では、「成長論から分配論へ」として、国家予算による無駄な投資をやめ、高福祉のための財源として、消費税・金融資産課税・相続税の大幅増税を実施すること(日本の国民負担率(40.6%、2008年)は先進諸国に比べてもまだ低い)。そして「市場メカニズムの尊重」として、個々の産業においては市場メカニズムに従い、非効率な企業を存続させず、雇用市場においても雇用・解雇にダイナミズムを持たせることを提案している。
著者の指摘の中で興味深かったのは、冒頭に引用したデンマークは、高い国民負担率によって世界最高水準の社会保障・社会福祉を維持していると同時に、ヨーロッパでは最も労働者を解雇しやすい国として認定されているという点である。要は、国際競争に勝ち抜くためにも企業は市場環境に柔軟に対応していく必要があり、人の雇用も例外ではないということだ。
「もちろんだからと言って、就労者は企業活動に供される単なる部品や材料のように扱われても仕方がないのかと言うと、それは全く違う。労働者は、従業員として企業に守られるのではなくて、国民として国家に守られるべきなのである。そのためのセーフティーネットが、公共財として国民全員に供される手厚い失業給付であり、十分な生活保護であり、医療・介護の無料化なのである。」
考えてみれば、戦後の日本は公共財としてのセーフティーネットが貧弱であっために、企業が長期安定雇用や社員教育を行うことでその代わりを果たしていたとも言える。だが、「失われた二十年」を経て、今の企業にそれを期待し続けるのは無理というものである。だから、これからは公共財を充実させねばならないと。そして著者は、ドイツやフランスのように恒常的な高失業率に悩む国からの教訓として、高水準の福祉と企業による雇用保護とをセットにしてはならない、という指摘も忘れていない。「高福祉だからこそ自由経済」という訳である。
著者の主張は結局のところ、「コンクリートから人間へ」というスローガンで昨年秋に政権を獲得した民主党の理念に近いものと言える。だから、
「これではバラマキが増え、福祉にぶら下がる輩が続出するだけだ。」
「昔から『働かざる者、食うべからず』と言うではないか。ブラブラしてる奴をなぜ税金で養わなければならないのか。」
「誰もが医・食・住を保障されてしまったら、誰も働かなくなるのではないか。」
というような反論は多々あることだろう。政権獲得後の民主党の実際の政策手腕については、著者自身も批判的ではある。
だが、私たちの頭の中がまだ成長フェーズにおけるモノの考え方から抜け切っていないことも確かである。その何よりの証拠に、「成長戦略がない」として民主党を批判する保守系の各党も、それでは自身の「成長戦略」は何かというと、法人税減税や規制緩和といった言葉以外には殆ど何もない。国民の幸福度をどのように高めていくかといった視点はあるのかどうか。ましてや、郵便局を守ろう、中小企業を守ろうとしか言っていない政党などは論外である。
折しも、来週日曜日の参議院議員選挙では、消費税増税の可能性が争点の一つになってきた。そのこと自体は以前に比べれば大きな前進である。国全体が成熟フェーズに突入している中で、個々の国民は果たしてどこまで成熟の度合いを見せていくだろうか。 本書はこれからも折に触れて読み返してみたい本である。
二つの新書 [読書]
「『文明は半島から来た』なんて大ウソ!」というサブタイトルからして挑戦的だ。本のカバーには、「日韓古代史の『常識』に異議を唱え、韓国の偏狭な対日ナショナリズムと日本のあまりに自虐的な歴史観に歪められた、半島史の新常識を提示する」とある。本書は元々、『戦後日本の朝鮮史学(者)を告発する』という仮題で倍の分量の原稿があったものを、出版社との調整でタイトルを替え、分量を半分にしたそうである。
時事通信社を定年退職した著者は、ソウル特派員として韓国に5年滞在。その間にいやな思いをしたことが少なからずあったのだろうか。日韓古代史の話だけではなく、韓国社会や韓国人の行動原理についても批判的な姿勢が節々に現れている。

といっても、よく見かけるような「嫌韓本」の一種ではない。9世紀に新羅が衰退した後、諸国分立を経て10世紀に半島を統一した高麗(918~1392年)が国家事業として編纂した、半島最古の正史『三国史記』と、それから百数十年後に、仏教を事実上の国教としていた高麗で僧侶の最高位に上りつめた一然(イルリョン、1206~89年)が『三国史記』批判のために著した『三国遺事』という原典にあたりながら、古代の半島と「倭」との関係を紐解いている。(今の韓国は自国の文字から漢字を廃止してしまったため、祖先がこうして漢字漢文で残した古典を読めなくなっているそうだ。)
そこから読み取れるのは、古代において半島南部はかなりの程度、倭人や韓人などの雑居する地域であったこと、新羅の第4代の王・脱解(在位:AD57~80年)は「倭国の東北一千里の多婆那国からやって来た」との記述があるように、半島には倭人が政権中枢に入り込んでいた国があったこと、そして、半島において「倭と陸続きの国」があった(⇒すわなち、倭の一部が半島にあった)ことだという。
古来、正史とは新たに登場した王朝が、自らの正統性を世に示すために編纂したもので、本来が政治的なプロパガンダを含んでいるものだ。その高麗王朝が、かつて倭人が新羅の基礎を作ったというような話を、もしそれがあり得ないような話だとすれば、それを敢えて正史に載せて正統性を疑われるような危ういことをするだろうか?というのが著者の論点である。
更に読み進んでいくと、半島では刀が長い間鋳造品であったのが、列島では早くから鍛造品であったことから、製鉄技術は列島の方が進んでいたと見られること、列島へのイネの伝播は半島経由でなく中国の江南地域からであることが今や明らかであり、水稲耕作の技術はむしろ列島から半島に伝わった可能性があること、中国大陸の前漢・後漢・魏・晋の各王朝が朝鮮半島の北西部に置いていた植民地・楽浪郡(BC108~AD313年)が古代においては文明の担い手であり、倭は半島南部を拠点に楽浪郡と通交することで文明を取り入れていたことなど、今まで漠然と聞かされてきた「文明は半島経由で列島へ」という構図とは異なる姿が見えてくる。
一方で、「倭」の方には独自の記録がなく、この時代の「倭」及び「倭人」が現在の日本及び日本人であるかのようにイメージしてしまうのも危険なのだろう。(著者の議論の展開方法は、このあたりがちょっと心配ではある。) 半島南部が倭人・韓人の雑居地であったのなら、九州北部から山陰地方などが(程度の差こそあれ)似たような雑居地であったとしても不思議はないのではないかと、素人的には思ってしまう。
日韓の古代史について、これまでの定説、特に韓国の学会が唱えてきたことを覆す本書の指摘。しかし読者が現在の「韓国」・「日本」という枠組みにとらわれていると、感情的な議論にもなるだろう。だが、歴史学も社会科学の一つである。ここはあくまでも冷静になって、「加害者」や「被害者」というバイアスをかけず、ましてや儒教的な観念論や偏狭なナショナリズムは排して、客観的な事実の解明が日韓の間で進むことを願いたいものだ。
時あたかもW杯サッカー大会の真っ最中である。頭に血が昇っている時は、こういう議論はやめておこう。
日韓での歴史観の違いに言及したついでに、この週末に読んだもう一冊の新書本、『日本人へ 国家と歴史篇』 (塩野七生 著、文春新書)の中に、ちょっと面白い指摘があったので、書きとめておこう。

「日米の間でも、近現代の歴史を共同で研究してはどうであろうか。
日韓ではそれをしたらしいし、日本と中国の間でも歴史の共同研究は始まったようである。だが私は、歴史事実は共有できても歴史認識の共有はむずかしいという理由で、日韓日中とも、カネと時間の無駄だと言ってきた。だが、やるべきでないとは言っていない。なぜなら、成果は絶望的でも、やっています、と示すことの有効性ならば認めるからである。ゆえに、これに使うカネと時間は、宣伝広報費だと思ったらよい。
ところが、日米間の近現代史共同研究となると話はだいぶちがってくる。しかもそのちがいは、すべてプラスになって返ってくる可能性まであるのだ。
まず第一に、アメリカ合衆国に対しては、本音はどうであれ建前としても、やっています、と示す必要はない。
第二に、あちら側の参加者たちには、始める前から頭に血がのぼっている人はいないだろう。
第三、硫黄島攻防戦は歴史事実で、それをどう見るかは歴史認識だが、この後者を強いて共有しようとしないで、アメリカ側と日本側の『認識』を二本立てにした、アメリカ人のクリント・イーストウッドという例がすでにあること。
なにしろ、敗戦後に行われた東京裁判で、ひときわ冷徹に論理的に、戦犯とされた人々を弁護したのも、アメリカ人の弁護人だったのである。
もしかしたらこのアメリカとならば、歴史認識の完全な共有まではできなくても、相当な程度に歩み寄ることは可能かもしれない。となれば、それに要するカネも時間も、宣伝広報費と思わなくてもよくなるのである。」
(「『硫黄島からの手紙』を観て」 より)
もっとも、直近の「日韓歴史共同研究」の進捗状況などを見ていると、ちょっと絶望的な気分になるのだが。
経年劣化 [読書]
最近の日本を見ていると、そういう思いに囚われることが少なくない。家畜の口蹄疫への危機対応も然り。企業のリコール問題も然り。蓋を開けてみれば次々に馬脚が現れた鳩山民主党政権の迷走ぶりは言うに及ばず、サッカーのサムライ・ジャパンも、2002年の日韓共催ワールドカップ大会で一度は決勝トーナメントに進んだ、あの頃に比べて何やら自信を失ってしまったように見える。この10年で日本全体の劣化が進んでしまったのだろうか。
そんなふうに書き始めてみたのは、作家の塩野七生氏が連載を続けている『文藝春秋』の巻頭随筆のうち、2003年6月から2006年9月までの40回分が『日本人へ リーダー篇』という新書本になった、それを読む機会を得たからである。

この随筆がカバーしているのは小泉純一郎首相の時代で、ブッシュが始めたイラク戦争の戦後復興支援に陸上・航空自衛隊を派遣するところから、自民党総裁の任期満了を以って総理を退任し、戦後3位の長期政権が終了するまでの3年3ヶ月。私達は日々のことにかまけていて、今はもう小泉時代の出来事すら忘れかけているが、この時期はイラクへの自衛隊派遣をはじめ、中国との間での靖国問題、竹中平蔵氏を起用した金融システムの早期正常化、郵政民営化の是非を問うた解散総選挙など、盛り沢山の課題があった。そして、それらに対して小泉首相が近年稀に見る強いリーダーシップを発揮して事に当たっていた時期でもあった。
「軍事とは所詮、自らの血を流しても他者を守ること、につきる。 (中略)
古代ではギリシアもローマも、本質はあくまでも、市民が主権者である国家であった。主権者であるからには、権利が認められる一方で義務も課される。権利は、選挙を通じての国政への参加であり、義務は、武器をもっての祖国の防衛だった。それゆえに兵役は、『血の税』とも呼ばれていた。 (中略)
湾岸戦争当時にわれわれ日本は多額の経済負担をしたにもかかわらず、クウェートから感謝もされなかったことでショックを受けたが、『血の税』の長い歴史をもつ側から見れば、ショックを受けたという日本人自体が不可解であったろう。」
(「イラク戦争を見ながら」 より)
この自衛隊のイラク派遣は、2001年9月の米同時多発テロへの報復としてブッシュ政権が始めたアフガニスタン攻撃をいち早く支持した小泉政権が、いわゆる「テロ対策特別措置法」を成立させて実行したものだ。但し、憲法第9条との兼ね合いから海外派遣の活動地域は「非戦闘地域と認められる公海とその上空・・・」に限られた。だから日本の貢献は「血の税」ではなかった。そもそも「ブッシュの戦争」に大義はあるのか、という声が少なからず上がったが、そこは首相が日米関係を強調して押し切った。
「もしも、誰でも納得できる客観的な基準に基づいた大義が存在するならば、人類はとうの昔に戦争という悪から解放されていたはずである。そうでないのは、もともとからして大義なるものが存在しないからなのだ。 (中略)
大義などはないのだ。といって、新秩序をつくる力はもっていない。この現実を見極めれば、やれることは限られてくる。他の国が大義と言おうが日本だけは心中でせせら笑い、それでいながら冷徹に国益を考え、その線で行動することだけである。」
(「戦争の大義について」 より)
「日本に帰国中に読んだ新聞の記事に、自衛隊は政治の駒か、と題したものがあった。私だったらこれに、次のように答える。そう、軍隊は国際政治の駒なのです。そして、駒になりきることこそが、軍隊の健全さを保つうえでの正道なのです、と。それゆえに、軍務に就いている人の誇りを尊重する想いと、その軍務は国際政治の駒であるとする考えとは、少しの矛盾もないと思っている。」
(「戦死者」と「犠牲者」 より)
軍事や外交はあくまでも政治の一つの手段なのだと冷徹に考えることが、我々日本人はなぜ不得意なのだろう。特に憲法第9条に係わる問題になると全くの思考停止に陥ってしまい、議論すること自体が悪であるかのような主張を続ける勢力が、今では政権与党の片隅に座っている有様である。憲法はあくまでも人間が作るもの。一度作ったものに現実と合わない条項が出てきたならば、その改正を是々非々で議論することの何がいけないのだろう。
「改憲派に多い、占領中にアメリカに押しつけられたものゆえ改める、という立場を私はとらない。占領後も、改憲しようと決心すればできたのにしなかった時期が半世紀も過ぎているのだから、もはやあれはわれわれ自身が望んだ憲法である。ゆえに改憲する場合は、今後とも『律法』的に考えるか、それとも『法律』的な考え方をとるか、のどちらかを、判断の規準にしなければならない。
もしも護憲を選択した場合は、ユダヤ教の律法が有効なのはユダヤ教徒の間だけであって、法律であったローマ法がもっていた国際競争力はついにもてなかった歴史的事実は、覚悟しておくべきだろう。」
(「法律」と「律法」 より)
(ここでいう「律法」とは、ユダヤ教における、神から人に示されてきた法典のことで、神聖にして不可侵、人間がそれを改めるなどもっての外、というものを意味している。)
時限立法であったテロ特措法は、安部内閣時代に自民党が参院選に大敗して「衆参ねじれ現象」が生じたため、福田(康夫)内閣時代に時間切れで失効している。そして、現在の鳩山政権は、普天間基地の移設問題という自国の安全保障に直接係わる事柄についてすら、徒に世論を弄んだ挙句に問題を泥沼化させてしまった。10年前、いや7年前と比べた首相の言動の軽さ、リーダーシップの欠如は見るも無残である。
小泉氏が政権から退いた後は、自民党内でのたらい回しのように首相が3度も交替し、昨年秋には「政権交代」までが起きた。しかし、鳩山政権の支持率は早くも危険水域に入っている。思えば、1993年8月の細川政権の誕生から現在まで16年と9ヶ月。その間に現在の鳩山氏も含めて11人が首相になった。在任期間は平均1年6ヶ月。一人で5年5ヶ月を務めた小泉氏を除けば、後の10人は平均1年2ヶ月に満たない。かくも頻繁に首班を入れ替えて、何かいいことがあっただろうか。ただひたすらに、日本の政治の劣化が進んだだけではなかったのか。
「ローマ帝国も三世紀に入ると、政策の継続性が失われたのである。具体的に言えば、皇帝がやたらと変わるようになった。 (中略)
危機の打開に妙薬はない。ということは、人を代えたとしても目ざましい効果は期待できないということである。やらねばならないことはわかっているのだから、当事者が誰になろうと、それをやりつづけるしかないのだ。『やる』ことより『やりつづける』ことのほうが重要である。
なぜなら、政策は継続して行われないと、それは他の面での力の無駄使いにつながり、おかげで危機はなお一層深刻化する、ということになってしまう。」
(「継続は力なり」 より)
塩野七生氏は、評論家ではない。古代ローマやルネサンス期のイタリアを専門とする作家である。だから、月一回の随筆を長年こなしていく中で、取り上げる話題には得手不得手があることだろう。私も、氏と必ずしも同じ意見ではない箇所は少なからずあるし、古代・中世の歴史上の事実がそのまま現代の諸問題の解決策になるとはもちろん限らない。だが、イタリアという地域の歴史の中で培われてきた、国際社会に対する醒めた物の見方というのは、私達としても参考にすべきことであろう。
それにしても、たとえ多勢に無勢でも一人で決断を下していた小泉氏に比べて、現首相はツイッターで呟やきを発信しているとは、何と小粒になったことだろう。
「自己反省は、絶対に一人で成されねばならない。決断を下すのも孤独だが、反省もまた孤独な行為なのである。」
(「プロとアマのちがいについて」 より)





